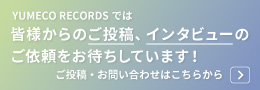――今回のアルバム『夢夢(ムームー)』に関しては何かコンセプトがありましたか?
藤田「今回は〈夢〉なんですけどね。結構、世代特有のモヤモヤ感みたいなものがあって。僕は今、27歳なんですけど、歳を重ねるにつれて生きていくのが大変になってくるんですよ。26~27歳ぐらいの同世代で集まって話たりすると、すごく悩んでるんですよ、みんな。僕らはもろ、ゆとり世代なんですけど、ディズニーランドが出来て、物心がついた頃に初めて行く世代が丁度僕らだったんですね。だから子供の頃の記憶として、まずディズニーランドが最初にある、っていうね。ディズニーやジブリといったワンダーランドが最初から頭の中にはあって、〈こんな風に大きくなるんだろうな、こんな世界が待ってるんだろうな〉って思ってたんですけど、でも大人になるにつれて全然違ってくるんですよ。その現実に対するジレンマがすごくあって、心がアンバランスになって病んじゃったり元気なかったりする人が周りにも多くて。僕は、そもそも音楽は身近な人に聴いてもらいたいなと思って作り始めることが多いので、〈夢〉をひとつのテーマにして、〈昔から知ってるのに現実にはない夢〉と、〈実際にこれから叶えていきたい夢〉を、音楽にして届けたらどんな風に伝わるだろう?って思ったんです。このエネルギーを一回まとめたいな、hotal light hill’s bandなら出来るなと思ったんです」
――なるほど。これまで藤田くんがRAVEで描いてきたロマンやファンタジックな世界とはまた違う、現実の中でどう夢を見ていくのかや、夢を見ることの難しさも含めて今回のアルバムは作られていますよね。
藤田「そうですね。曲を書くことそのものは、最初はファンタジーだったんです。でも生きていく上で周りから色んな攻撃を受けるし、仕事もしなきゃいけないし、決して順風満帆なわけではないんですよ、毎日が。東京で生活してた時は特に、ただ生きてるだけで色んな外敵があった。情報もすごいし、それで僕は、途中でテレビを粗大ごみの日に捨てたんですけど。何か、欲しかったものが全部いらなかったんですよ。あったらいいなと思うものが、全部必要なかった。〈じゃあ何が残るんだ?〉って考えた時に、最終的にやっぱり音楽が残るんですね。これしかないんだな、と思って。RAVEを始めた時の自分はどんどんすり減ってしまって、一回全部粉々になったんです。そこで元々暮らしていた街に戻って、曲を書き始めると、また一から全部、自分でわかったんですよ。〈あ、これは必要だな、これも必要だな〉って。色んなことを難しく考えすぎてたな、結構簡単なんだなって思えたんです。今の僕だったら、小さいこともよく見えるから、モヤッとした気持ちにもちゃんと向き合ってみようかなと」
――世代感とか夢と現実とか、色んな要素があって。でもこのアルバムのひとつの希望となっているのは「君」という存在ですよね。「君がいるから夢を描けるんだよ」っていうことが、このアルバムを照らしてると思うんです。
藤田「なんか僕、ずっと歌の理想形がひとつあって。〈君〉という言葉が、もう一人の自分と一緒じゃないと嫌なんですよ。〈君〉に好きって言うのは簡単なんですけど、その人がもう一人の自分にもなり得る、ということが、本当に愛してるってことだと思うんです。大好きになった人って、やっぱり自分が乗り移るから、自分の嫌なところが相手から見えたりとかするんですね。そういう意味で、いつも思ってたのは〈君〉を自分に置き換えてもちゃんと当てはまるか、いつも歌詞を読み返してたんです。で、そうじゃない曲は歌いたくない。それが今になっては、もう考えなくても出来るようになったんですね。今は何だか18歳の頃のような気持ちで、世界は素晴らしいと思えるし、愛って何だろうとか色々考えてたけど、実はシンプルなことで、愛はすぐ側にあると思えるんです。自分の中の光をお互いに探しあうような気持ちをいつも忘れたくないし、それも夢を見ることと同じだなって」
――「君」と歌いかける時に、それが自分にも当てはまるのかどうかを最近はあまり意識せずにやれるようになった、というのは、ツインボーカルになって、もう一人の声が聴こえてくることと関係してるのかな?って思ったんですけど。
藤田「うんうん、そう思います。ボーカルが二人いると、〈ただ唄う〉とか〈ただハモる〉ってことをしなくなりました。もう一人の自分を友香に飛ばしてるような、そんな感覚の時もあります。乗り移らせていただいてる(笑)?」
――なるほどね。でも、そもそも特に将来なりたいものがない、見つからない人とかもいて、夢を語る人に「夢があっていいよね」って思う人もいるわけじゃないですか。そういう人のことも無視してない作品だなと思うわけですよ。
Max「そういう人が大多数な気もしますけどね。自分もよくそういうこと言われますもん、漫画の仕事してるとかって言うと〈夢があっていいね〉って」
藤田「漫画しかり、音楽しかり、芸事って全部、〈夢〉って言われるじゃないですか。僕も〈そんなに夢見がちに生きてて大丈夫?〉とかって言われるんですけど(笑)。でも夢のある仕事って結局は自分自身を燃やす、エネルギーのいることだと思うんですよね。人それぞれだと思うけど、間違いなく言えるのは、大切にしたいものがある人は、それがまず夢になるはずなんですよ。大切にしたいものに対して自分を注いでいくことがそもそも夢なので。夢を見るっていうことが方程式みたいになりすぎてるんじゃないかなって僕は思うんですよ。イコールなんだ?みたいな、そんな巨像をイメージしすぎてる。夢を見ることは、ご飯を食べたり、恋をしたりするのと同じ、行為なんですよ。一回ちょっと、今まで与えられてきたことを忘れて、ここで考え直さなきゃいけないなっていうことのひとつが〈夢〉という言葉に集約されてるなって思います」
☆☆ちなみに漫画家のアシスタントってどんな仕事?☆☆
――Maxさんはいつぐらいから漫画を描いて生活したいなと思ったんですか。
Max「自分の場合は漫画家じゃなくてスタジオのスタッフという形なんですけど。もともと小学校3年生の時から漫画を描いていて、漫画家になりたいと思ったんですね。それで、世間の噂だと大学生くらいになると暇になるらしいから(笑)、そのぐらいのタイミングで何とか漫画家になろうと計画していて、ずっと描き続けてたんですけど。でも中学生くらいになるとピタッと何も描けなくなってしまって。漫画家になりたいと思ってたけど、結局、何を描きたいのかなと自分の中を探ってみると、描きたいものってあんまりないなと思ったんです。それで悶々として、大学の時も作品を投稿しようと試みたけど、やっぱりダメで。もう辞めようと思って諦めてたんです。でも漫画研究会に入って、今、付いている先生が大学の1個上の先輩なんですけど。その先輩が漫画家としてデビューするから、手助けして欲しいって言われて。自分の作品とは言えないけど絵を描いてお金を貰えるのはいいなと思い(笑)、それでそのままスタジオ勤務して今に至るっていう感じです」
――身近な方が漫画家として成功されるっていうのも、すごく珍しいことで。ある意味、ラッキーですよね。
Max「そうなんですよ。その先輩と同じ学年の人もこないだアニメ化された漫画家さんだったりして、スーパー世代なんですよ(笑)。別に美大とかじゃないんですけどね。でも先生と一緒に仕事をしていくうちに、自分はアクション・シーンとか描くのが大好きなんだなとか、色んなことに気付いていったんです」

こちらは以前、Maxさんが個人で作られた同人誌
――漫画家のアシスタントさんって、どういう生活なんですか。
Max「それがたぶん、みんなわからないと思うんですけど(笑)。言葉としてアシスタントっていうと〈ベタ塗ってるの?〉とかよく言われるんですけど。うちのスタジオは割と特殊でスタッフがちゃんと役割を持って分担作業をしていて。下書きを担当する人がいて、背景とかだと写真を撮ったり調べたりして描いて、それをまたスクリーントーンを貼ったりして仕上げていく人がいて。小さい1コマでも一日がかりで描いてたりするんですよ。特にうちの漫画は細かくて、アクション・シーンが多いので、もうネチネチやってますよ(笑)」
――チーム全体でひとつの作品を描いてる感じなんですね。
Max「やっぱり週刊の連載とかだと一人じゃ描けないですからね。でも漫画家として最初に突破口を開くのは先生一人なので。そこで成功すればチームを作って週刊や月刊に挑むわけです」
――なるほど。Maxさんは実際に漫画のお仕事をしていく中で、夢と現実とのギャップってありましたか。
Max「ありますよ。〈え、そんな簡単に台詞を変えられちゃうの?〉とか、やっぱりこの世界に入ってから知ったし。描きたいものを描けるわけじゃないんだ、とかね。好きなことを仕事にした故の葛藤ももちろんあると思いますよ。本当は自分の納得のいくまで絵を完成させたいけど、漫画家は締め切りがあるし、全部のページを自分だけで、っていうのはやっぱり無理ですからね。でもアシスタントだと、そのひとコマを全力で描けるっていう、その満足感は、すごく大きいです。もちろん、それが自分の作品とは呼べないことへのジレンマはあるし、自分でも描かなきゃな、とは思うんですけど、それが商業ベースとして成功するかと言うと難しいだろうし、という葛藤はありますけどね」
――漫画家のアシスタントという仕事は狭き門ですか。
Max「漫画家として食べていけてる人が、そもそもほんの一握りの人って感じがしますね。漫画家も格差社会で売れてる人は売れてるけど、ほとんど売れてない人の方が多いからバイトをしながらじゃないと生きていけないという人もたくさんいますよ。幸い、自分の先生の作品は海外でも売れていて、海外版ではスタッフの名前もクレジットされているので、そういうことが〈自分も役に立ててるのかな〉という喜びだったりします」
藤田「僕はMaxさんが描いた、天空都市みたいな絵を最初に見せてもらって、すごいな、この人は漫画と人がすごく好きなんだろうな、と思った。あと、星が好きそうな顔してる」
Max「ええっ(笑)、星は好きです。『銀河鉄道の夜』がすごく好きなんですよ。『少年賛歌集』のジャケの時にも、そんな話しましたね」
――なんかそういう共通した世界観があるんだろうな、と思いますよ。お二人には。
藤田「うん、そういうの大事ですよね」
――では最後に、ホタバンの今後の展望など。
藤田「とにかく曲を書いていて、今もう40曲ぐらいあるんですよ。今回の『夢夢(ムームー)』は〈作るぞ!〉と思って作ったので、次の作品は書きたいように書いてみて〈さあ、どうしよう?〉ってやろうと思ってるんですけど。今、ワァーッて出てくるものを止めたくないな、と思うんですよね。自分の中で第二次ピークが来てるんで(笑)」
――それは今の環境であり、メンバーがいることで訪れた第二次ピーク?
藤田「メンバーですね。バンドなんですよね、やっぱり。一人でやっても何にもないんです。バンドじゃないと書けないものがあるから、それをすごく大事にしたいし。色んなことのひとつひとつが偶然に思えなくなってきてるから、大事にしないとなって思ってる。自分で曲を書こうとする力が、消えないでちゃんとあるんです。〈もう辞めてやろう〉なんて思ったこと、一度もないですし、自分に嘘は付けないですから、ずっと出し続けたい」
――バンドの状況とか、ある意味関係なく音楽がやれてるんでしょ?やりたいからやる、っていうシンプルなところで。
藤田「そうそう、そうだと思います」
――藤田くんは辛い時期もあったんだろうけど、耐えたんだと思うんです。それで、やっぱり音楽がやりたいっていう気持ちが勝ったんだと思う。
藤田「すごい勝ったと思います。誰もが天才だと思って音楽を始めるんだと思うんです。17~18歳ぐらいの時に〈俺はすごい!〉とか思って。でも天才じゃないな、って気付く時が来るんです、それが遅かれ早かれ。俺はそれがつい最近来たんで遅かったなと思って、人より。やっぱり誰かに認められたり結果が出ないと、音楽って成立しないし意味がないなってちょっと思ってた時もあったんですけど。でもそういう感情が消えると、色々見えてきて」
――うん。今って、そうした結果うんぬん以上に自分の中に音楽をやる価値を見いだせる人が残って、それが出来ない人は辞めていくんだと思うんですね。
藤田「確かにそうだと思う。やっぱり、音楽をバカにしたくないですからね、俺は。そしてhotal light hill’s bandっていう看板があれば、今は何でも書けるような気がしています」

藤田くん、Maxさん、ありがとうございました。柏カフェラインさんにも感謝。
☆☆hotal light hill’s bandのアルバムは1枚1000円(税込み)。彼らは今、その売り上げが次の作品を作るぶんの収入にさえなればいいと言う。純粋な気持ちで音楽と向き合った結晶のような1曲1曲を、是非多くの人に聴いてもらいたい。値段は音楽そのものの価値ではないと、つくづく思う。彼らの描いた夢が誰かの日常にある夢を少し色づけ、少し動かすはず。それをイメージすることだけでも、とてもワクワクする。
オフィシャルHPはこちら↓↓(音源もこちらで販売中)
まっくす●Max。東京都在住、8月9日生まれ。中央大学卒業後、某漫画家スタジオでアシスタントとして勤務する絵描き。個人サークル「夕暮れ剣士」として創作マンガ等をコミケで発表している。シルバーアクセ好き。