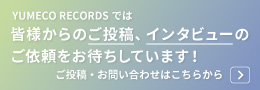昨年2月にRYTHEMを解散した後、新津由衣がソロ・プロジェクトとしてNeat’sを立ち上げた。約半年に及ぶ制作の後に完成した1stアルバム『Wonders』は、今年の1月28日よりオフィシャルHP (http://www.neatsyui.com/)にて販売されている。全ての作詞・作曲とアレンジはもちろん、ジャケットのデザインからミュージック・ビデオの監督まで手がける、セルフ・プロデュース。RYTHEM時代から聴かせてくれていたポップなメロディ・センスはそのままに、とことん自分自身と向き合った歌詞世界は、愛に怯え孤独と嘘に飲み込まれそうになりながらも、バンド・サウンドが描き出すファンタジーに明日を夢見る。そんな、ちょっと壮絶なんだけど非常にチャーミングな1枚に仕上がっている。「ゼロになっちゃったの」――そんな告白から始まるこのインタヴューでは、彼女がソロになって今作を作りながら葛藤してきた自身の想いを語ってくれた。RYTHEMの頃の彼女を知る人は、ちょっとびっくりするかもしれない。今回はロング・インタヴューを前後編でお届けします!(撮影/平沼久奈)

Neat’s アルバム『Wonders』インタヴュー(前編)
――アルバム『Wonders』、聴かせていただきました。ここまでクリエイティヴィティに溢れたもので、なおかつ自分自身にとことん向き合っていく作品っていうのは、生半可な覚悟では作れなかったと思うんですけど。
「そうです、すごく。だからその覚悟が、作ってる最中でも〈こんな覚悟じゃ足りないんだ!〉って思って何度も自分を崩されたような期間だったんですよね、作ってる半年間は」
――ソロになって、まず何をやろうと思われたんですか?
「やりたいことは、たくさんあって。こういう世界を表現したいな、とか、あったんですけど。ほんとにやってみてわかったのが、私、何にもなくなっちゃったんです。やりたいことが何なのかさえわからなくなったくらい。自分が信じてたものがボロ崩れした感じで。何て言ったらいいんだろう……さっき〈生半可な覚悟じゃ出来ない〉って言われましたけど、ほんとにその言葉に尽きるんです。しっかりと生きて、しっかりとアーティストとして表現していくっていう覚悟は生半可な覚悟じゃ、やっぱり出来ないもので。もちろん自分では、そんな生半可な覚悟だとは思ってないんですけど、あらゆるところで崩されるんです。自分が積み上げてきた経験とか過去とかでは何も生まれないんだってことを感じて。もう、ぽっかりゼロになりましたね。マイナスになっちゃったかもっていうぐらい」
――ただ、こういうアートワークも含めたトータル的な世界観を提示するっていうのは、もちろん一朝一夕では出来なかったと思うんですね。ずっと前からこうした表現したいものが心の中にあったんじゃないかなと。でも、ご自身の中ではゼロになった感覚があったんですか?
「このアルバム制作をしながら、子供の時からずっと感じていたところに辿り着くまでの距離がすごく長くなってしまったことに気が付いて。私は子供の心を自分の軸として持っていたはずなのに、やっぱり自分は知らない間に大人になっちゃってて。子供の時にしか見えないものとか、感じられないことを、絶対に大人になっても捨てるもんか、と思って、もう半ば意地になって生きていたところがあって。〈絶対に大人になんかなるもんか!〉〈向こうの世界は汚いから絶対に行くもんか!〉って、そうやって色々と壁を作っちゃったんですよね、逆に。そうしてたことで自分が純粋だと信じてたのに逆に真っ黒というか、壁だらけトゲだらけの自分だってことに、どんどん気が付いたんです。だからもともとあったものを表現したいと、私自身も思って『Wonders』を作り出したけど。もともとあったものを守りたかった為にトゲだらけで、純粋なんてもんじゃない真っ黒な人間になってたことに気付いて。それで自分の武器が何なのかわかんなくなっちゃったんですよね」
――それは、例えばRYTHEMとして活動していく上で変わらなきゃいけなかった場面っていうのも多々あったと思うんですけど、そういうことも影響していますか?
「それは少なからずあると思いますね。やっぱり、大衆音楽としてやっていく、そしてチームの人数が多ければ多いほど色んな意見があるし。その真ん中に立つものとしては、それを最終的に解釈して表現するのは自分だから、自分の表現の中にどうやって組み込んで行こうか?とか、クリエイティヴとは別のベクトルで色んなことを考えて行かなきゃいけないっていうところで、守っちゃってた部分もあると思う。でもそれよりも、もっと無意識なレベルで自分が自分に壁を作ってたんだと思います。人との距離をすごく難しく図ろうとしてるっていうことに気付いちゃって。それをどうやって崩したらいいかがわかんなかったんですよ、ほんとに無意識だったから。無意識に仮面を付けちゃってる感じ。人がいたら笑わなきゃとか、人がいたら盛り上げなきゃとか、変な仮面をずっと付けてるような感じだったことに、制作の途中でようやく気が付いたんです。〈私、自然体じゃない!〉って」
――それは何かきっかけがあったんですか。
「〈何かあなた不自然だね〉って人に言われたんです。それを言われて、私自身もそう思った。それからは何がどう、そんな風に思わせちゃうんだろうと毎日自分に向き合って、知らなかった自分に、知りたくなかった自分に気付いて。もう涙しか出ない(苦笑)」
――何が不自然だと思われたんだと思います?
「何にもないくせに、何でもあるような気分でいるの。あはははは!」
――ある意味幸せじゃない(笑)?
「うーん、それに気付かなければ幸せだったかもね。でも今の私は何もない。どうしようって思ってるけど、しょうがないなって。私はまだ26年しか生きてないけど、その中でも色んな経験をさせてもらって、何かしら知識だったり自分の武器みたいなもの、オリジナリティみたいなものを持ってるもんだと思って、少し自信を持っていた気がしたんだけど、そんなの間違い。何にもない。そういうところに目を向けちゃうのも不安をどうにかして凌ぎたいからで」
――でも今までやって来たことは目に見えないものも、形になっているものも、ちゃんと残ってるでしょ。それは自信にならない?
「自信にして、その瞬間のエネルギーとして頑張るぞって思ったり安心したり、それぐらいにしかならないかな」
――根底のところで「大丈夫」って思えるものではないんだ。
「ない。それはいつまで経ってもないかもしれない」
――あのー……前からそういう性格でしたっけ?
「あははははは、残念ながら!そうなんです。でも、そういうのを表に出すことをすごく恐れてたから、仮面を付けてたと思う。そういう風に思われたくなかったし、そういう自分だって知られたらいけないんだっていう変な先入観もあったし。〈大丈夫ですぅー!〉みたいな感じで(笑)、やってたね。でももうそれが習慣になってたから辛くはなかったけど。ほんとに覚悟を決めて、ほんとの自分で、こういう風に、ちゃんと音楽と向き合うってなると、そんなことやってられないなって思ったんです」
――だから、この『Wonders』には、ほんとの新津由衣が入ってるよね。
「そう思います。この作品を聴いて、〈この人は何て生き方が不器用なんだ〉って、言ってくれる人の言葉を聞くと、正直ショックですけど〈あ、伝わってるな〉って(笑)。自分でも最確認しました。私はやっぱりそういう人なんだから、そこから逃げちゃいけないなって」
――そういう意味では意外に思う人がたくさんいると思うんですよね。
「そう思います。私も意外で泣いちゃうんです。〈あれ…私こんなんじゃないもん!〉って。もう……最近インタヴューの度に涙が出てきちゃうんですけど……」

――でもご自身は特にRYTHEMの後半ではたくさん、作詞も含めて曲を書かれていたし、デビュー当時よりも、よりリアリティのある作品作りをされてきたと思うんですけど。それでもRYTHEMをある意味プロデュースしている、そしてRYTHEMのYUIであることを自分自身も演じているようなところがあったって感じなんですか。
「うーん……そうですね、やっぱり責任感みたいなものに動かされているところはあって。自分を表現するんだというよりはRYTHEMというものの形を使って、どうやって人を感動させられるんだろう?みたいな、いつもすっごい距離感を保ちながら見てた感じだったから。特に最後の方はそうなんです」
――RYTHEMのYUIちゃんって、すごくキラキラしてるイメージだった。太陽の下で真っ直ぐな恋愛をしているような。
「そうですね、キラキラしてる感じ……でも、恋愛の曲とかは、本当に書くのが苦手で。自分を女性と認めたくないんですよ。つい2ヶ月くらい前に、ようやくそこを越えようと思い始めたばかりなくらいです。だからそういった面では、例えば昔に作った恋愛の曲で〈YUIちゃんはこういう恋愛をしてるんだ!キラキラ!〉っていう印象は、それは私ではないかも」
――あははははは!言うね。それはもう、ポップ・ソングとして作ったと。私ではないと。
「うん、RYTHEMを守るために」
――で、今はその守るものもなくなって、出てきた自分自身にびっくりしたと。
「うん。何にも守るまいと思ってたけど意外に自己防衛本能っていうのは避けられないもので。曝け出すぞって覚悟をしながら自分を良く見せようとか、かっこいいアーティストだと思われたいみたいなところから、変に取り繕っちゃったりしちゃうの。そんな自分がほんとに最悪に嫌いで。それをどうにか打ち崩したいと思ってる。今も反射神経的に出ちゃう時があるし、こうしてインタヴューとかしてもらって、毎回、自分でもちゃんと壁を破れよ、って思うんだけど、なかなか難しくて。意識しないとシャットダウンしそうになるから、ダメだ、ちゃんと開いて行きなさい!ってお尻叩きながらやってる感じ。だから毎回本気で向き合ってるつもりなんだけど、たまに嘘が出てるかもしれない(苦笑)」
――逆になんでそこまで正直にならなきゃと思ったんだろう?
「そうしないと自分が音楽をやる意味がないと思っちゃう」
――ソロでやって行く上でのテーマとしては、やはりそこなんでしょうね。
「そうですね。嘘をつきたくない。それに尽きるかな」
――そういう想いに誠実な1枚が出来たのはすごいなと思います。
「うん、このアルバムはだから、かなり不安定な感じだと思う。私から見ても、色んな人格が出ちゃってる感じで(笑)。自分の壁にバーンッとぶち当たって〈あ、こっちじゃなかった!〉って〈あ、こっちも痛い!〉みたいに自分でぶつかって行ってる感じだし。ほんと自分の中を冒険してる1枚だと私は感じる」
――でもサウンド作りは楽しくやれたんじゃない?
「うん、やりたいことがあって、作りたいサウンドがすごくあって。そこに対しては客観性をすごく持ってたと思う」
――そこが良かったよね。
「そうかもねー。私、やっぱり自分のことを伝えたいが為にやってるんじゃないんだと思っていて、そうしたくなかったの。一人よがりの音楽みたいになっちゃいそうだし、しかも今まですっごいポップなことをやってたからなおさら、YUIちゃんってコアな方に行きたかったのね、って思われても、そういうことではないから、私がやりたいのは。だからサウンド面に関しては〈これにポップな要素を足したらどうなるんだろう?〉とか〈これとポップの間はどこだろう?〉とか、すごくバランスを取ろうと客観視してたかな。でも出来上がってみて、私自身が持つメロディって、結構やっぱりポップなものが多いので」
――そうですね。
「もうちょっとアレンジ的にはドスが効いても良かったかなって今思ってるから、次はそういうのも作りたい」
――だからどんなに、孤独や臆病さを正直に言葉にしていても、やっぱりメロディがポップだから、そこに救われてますよね。
「うん、そうですね。私自身、この1枚で、そこはすごく自分のいいところとして見つけられたところなんです。メロディだね、やっぱり。それは自分の武器として育ててあげたいなと思う」
――このバンド・サウンドの感触とか、エレクトロ・ポップのファンタジックな感じとか、ご自身のセンスがすごく発揮されてるなと思います。
「でもやっぱり足りないの。私が出来る範囲のところはここまでで。もっとその世界にグワッとのめり込んでる人たちのサウンドって、やっぱり真似できないし。私がやると〈ごっこ〉になっちゃうところがあって、それがいい部分もあるんだけど。なんか、次はね、しっかりサウンドの泥に首を突っ込みながら私のメロディを歌うっていうことをやってみたいですね」
――そういう意味では次にやることも明確ですね。
「そうですね。これが作れたことで見えてきました」