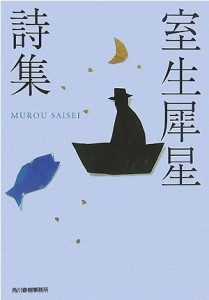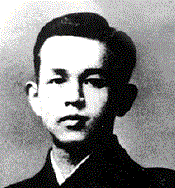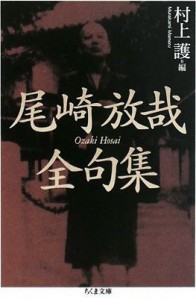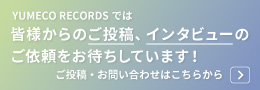「ふるさと」というお題でまず頭に浮かんだのは、有名な室生犀星の詩と石川啄木の短歌でした。
室生犀星の方は、「小景異情」(『室生犀星詩集』所収)にある
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食(かたゐ)となるとても
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
という部分。
室生犀星の場合、生い立ちが複雑なので、「帰るところにあるまじや」になるのかもしれません。「遠きにありて」とあるので、自然とふるさとの土地としての面が印象に残ります。生まれ故郷や幼い頃を過ごした土地などを思い出させてくれます。
 ちなみに、室生犀星は没後50年が過ぎて今年パブリック・ドメインになったので、これからは作品に触れる機会がさらに増えるでしょう。「蜜のあわれ」(『蜜のあわれ・われはうたえどもやぶれかぶれ』所収)などの小説ももっと知られるようになってほしいものです。
ちなみに、室生犀星は没後50年が過ぎて今年パブリック・ドメインになったので、これからは作品に触れる機会がさらに増えるでしょう。「蜜のあわれ」(『蜜のあわれ・われはうたえどもやぶれかぶれ』所収)などの小説ももっと知られるようになってほしいものです。
ふるさとの訛りなつかし
停車場の人ごみの中に
そを聴きにゆく
という一首を思い出しました。確かにお国言葉もふるさとを感じる要素の一つでしょう。
石川啄木はこのような鼻の奥がツーンとなるような短歌を多く残してますが、実生活のダメ男っぷりがこれまたすごくて作品との落差に唖然としてしまいます。もしかすると知らない方がいいかもしれません。でも、どんなダメ男っぷりかに興味を持った方は、谷口ジローの『『坊っちゃん』の時代第三部』や石川啄木の『ローマ字日記』をどうぞ。個人的にはこの落差が大好きです。文芸の芸たる部分が凝縮されているような気がしてなりません。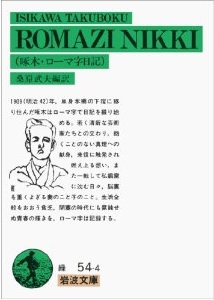

さて閑話休題して、池内紀は『出ふるさと記』の序文で学歴や名声などもふるさとなのだと書いています。そして、序文の最後を「ふるさとを持たないで老いるのは酷いことだ。」と締めくくっています。
この本は作家とふるさとの関係を探ったもので、安部公房、坂口安吾など計12名の作家が取り上げられており、人口比率からすると不思議なことに、今、私が住んでいる鳥取から2人選ばれてます。『第七官界彷徨』の尾崎翠と自由律俳句の尾崎放哉。昔も鳥取から多くの人が離れて行ったんでしょうか。その結果として人口最少の県が残ってるのでしょうか…。そんなことをぼんやり想像しました。
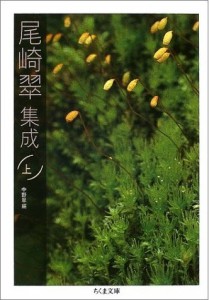
 尾崎翠は河出文庫に『第七官界彷徨』が収められてますし、ちくま文庫には『尾崎翠集成 上巻』『同下巻』があります。そういえば、数年前には尾崎翠のシナリオをもとに津原泰水が『琉璃玉の耳輪』を書いてました。ありふれた言い方になってしまいますが、時代を超えた作品を残した方です。
尾崎翠は河出文庫に『第七官界彷徨』が収められてますし、ちくま文庫には『尾崎翠集成 上巻』『同下巻』があります。そういえば、数年前には尾崎翠のシナリオをもとに津原泰水が『琉璃玉の耳輪』を書いてました。ありふれた言い方になってしまいますが、時代を超えた作品を残した方です。
尾崎放哉はというと、ちくま文庫に『尾崎放哉全句集』が収められてます。自由律俳句ってまた違った面白さがありますよ。「咳をしても一人」や「墓のうらに廻る」なんて、はじめて目にした時はギョッとしたもんです。
生まれ故郷の東京を離れて米子で10年ほど暮らしているんですけど、何でふるさとを感じるかといえば、東京の街角のちょっとした風景ですね。30年前には実家周辺でも、商店街でもないのに数分歩けばパン屋、八百屋、薬屋、酒屋がありましたが、今じゃ全部たたんでしまいました。そんな頃の記憶をうまく刺激するのがなぎら健壱の『町の忘れもの』です。写真がいい味出してます。ツボにはまった時には記憶の大洪水です。
あとは、李白の「静夜思」(『李白詩選』所収)にある「頭を挙げて山月を望み/頭を低(た)れて故郷を思う」にグッとくるようになりました。
記憶を残す建物も消え、記憶を共有する友人も亡くなり、記憶を宿す物もなくなっていき、最後は頭の中の記憶だけが頼りだけど、それもだんだんとあやふやになっていく…。悲しくもあるけれど、そこまで長生きできればそれはそれでしあわせなんだろうなあ。
のま・つとむ●東京生まれ。米子在住。学校図書館に勤務。通勤の車中で音楽を聞くことが多い。日本海側の冬景色を感じつつ運転していると、不思議なものでアストル・ピアソラのタンゴが心にしみます。最近は彼の『ベスト・セレクション』を愛聴してます。