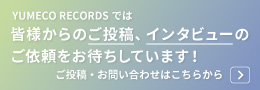ロック・バンドのスタイリッシュさ、上品な背徳性。そういったものに魅せられる人は時代が変わっても尽きないでしょう。以前は、このYUMECO RECORDSにて僭越なことにくるりを紹介させて戴きましたが、今回は同じく、バンドとしての産声が京都から生まれ、UKや東京でじわじわと評価を受けているLillies And Remains(リリーズ・アンド・リメインズ)というバンドを紹介させて戴ければ、と思っております。現在のメンバーはVo/Gt.のKENT氏、Gt.のKAZUYA氏、Ba.のNARA MINORU氏。主に、詞・曲はフロントマンであるKENT氏が担います。知名度的にはまだまだかもしれません、ちなみに、Lillies And Remainsとは、ゴシックの始祖とも称されるバウハウスというUKのバンドの曲名からインスパイアされているのでしょうが、当時の取材では、文学的な響きを感じたので、という言葉を残しています。当初、2007年に人伝手に私が学部時代にお世話になりました京都の同志社大学のバンドの中でクールな新しい音を鳴らしているのが居る、というのを知り、関心を持ち、My Spaceのページで音源をチェックしてみましたら、そこには幾つかの音源と、徹底したヴィジュアル・コンセプトが設定されていました。そのヴィジュアル・コンセプトとは、15世紀から16世紀にかけての、ルネサンス前の中世建築やアートに中指を立てたアントニオ・フィラレーテやジョルジョ・ヴァザーリのような高貴さとゴート風な全体像と言えると思います。それは、当時のメンバー全員が同じ大学で出会ったという事実から、同大の今出川校地内にある有名なクラーク記念館を通じ、ドイツ・ネオ・ゴシック様式に魅せられた「よくある学生たち」という感じもしました。(※なお、この初期の四人のメンバーから現在も居るのはフロントマンのKENT氏のみです)
 翌年に、ライヴを初めて観たのですが、演奏は拙いものの、低温火傷を起こさせるようなパフォーマンスで細身のスーツ姿の四人の佇まいはとても恰好良く、しっかりと真摯に音楽に対峙している姿勢には好感を持てました。大きく言いますと、セカンド・アルバム前のUKのザ・ホラーズ辺りとも共振もしていたのでしょうし、スーサイド、ジョイ・ディヴィジョンやインターポールといった翳りを持った舶来のオルタナティヴ・バンドの匂いを強烈に感じもしましたし、歌詞世界の描写はザ・キュアーのロバート・スミスではないか、という英語詞の滲みがありました。同時に、ようやくのこと、堂々と胸を張り、暗闇をそのまま進むかのようなエレガンスをBUCK-TICK的に格好良く鳴らすことができる日本のバンドが出てきたという事実に、シーンの変化の胎動も感じることができました。それは、当時の世界を覆っていました、MGMT、ヴァンパイア・ウィークエンド、フォールズなどニュー・エキセントリック・シーンと呼ばれながらも、すべてが一括りにはできない独自の盛り上がりの中で、ミドル・クラスの子たちが敢えて、ロックンロールをやるという意味が私の中で再定義出来てきていたという背景もあった気がします。
翌年に、ライヴを初めて観たのですが、演奏は拙いものの、低温火傷を起こさせるようなパフォーマンスで細身のスーツ姿の四人の佇まいはとても恰好良く、しっかりと真摯に音楽に対峙している姿勢には好感を持てました。大きく言いますと、セカンド・アルバム前のUKのザ・ホラーズ辺りとも共振もしていたのでしょうし、スーサイド、ジョイ・ディヴィジョンやインターポールといった翳りを持った舶来のオルタナティヴ・バンドの匂いを強烈に感じもしましたし、歌詞世界の描写はザ・キュアーのロバート・スミスではないか、という英語詞の滲みがありました。同時に、ようやくのこと、堂々と胸を張り、暗闇をそのまま進むかのようなエレガンスをBUCK-TICK的に格好良く鳴らすことができる日本のバンドが出てきたという事実に、シーンの変化の胎動も感じることができました。それは、当時の世界を覆っていました、MGMT、ヴァンパイア・ウィークエンド、フォールズなどニュー・エキセントリック・シーンと呼ばれながらも、すべてが一括りにはできない独自の盛り上がりの中で、ミドル・クラスの子たちが敢えて、ロックンロールをやるという意味が私の中で再定義出来てきていたという背景もあった気がします。
ここまで、多くのバンド名が出てきましたが、殆どが日本のものではありません。カテゴリーとしての邦楽/洋楽というものを考えてみますと、洋楽となってしまうのでしょうか。日本語で歌うこと、それは日本人だとやはり心に響きます。ただ、ときに洋楽と言ってしまうと、「言っている内容の機微が分からない」など英語を代表とした他言語の溝はあるとは察しますが、皆さんも知っていると思いますハイ・スタンダードやエルレガーデンといったパンク・バンドは姿勢として英語で歌いますが、オーディエンスはしっかりそれを分かり、受けとめ、ともに歌います。最近では、ザ・ボウディーズは渋いR&Bをベースにした形でロックンロールを全うし、今の景色を切り取って、多くのファンを得ています。K-POPもそうですし、カテゴライズすることで手に取り易いものがある分、看過することも増えています。若い子たちと話をしていてますと、「英語は分からないから。洋楽はよく知らないから」という声を聞くときに私は、その子たちが愛しているバンドが好きなアーティストやバンドを知っていくと、色んな気付きがあるよ、と言うことにしています。
さらに、日本でやはり、ゴシック系の音を鳴らすのは正直、カルト的な意味合いを多いに含みます。ともすれば、すぐヴィジュアル系と侵食し合ってしまいますし、また、デモーニッシュ(魔的)なものが現前しているアメリカやUKでは成立しましても、そういった「デモーニッシュな何か」を持ち得ていない、この国だと「ただ、暗いだけ」の音楽で片付けられる可能性もあるのは実際に海外のそういう人たちと話せば、分かることがあります。例えば、インダストリアル・サウンドの嚆矢たるナイン・インチ・ネイルズ、世界的に人気の高いベテランのバンド、レディオヘッドのライヴに足を運んで、確実に少なくない数でいる黒の誘惑に魅せられた集まり、彼らの文脈で、意味が付与されているバンドの音の回収のされ方とも繋がってきます。勿論のこと、それは各々の信条、生き様、宗教性にも連関してくるので私は良いと思いますが、日本という独特な島国で基本的に、成立しにくいのはカタルシスが別ベクトルにあるという快楽の問題だけに依拠してくるというのもあります。「神」とは寧ろ、八百万(やおよろず)と言われたりする訳ですから。KENT氏も好きな、アメリカのインターポールのストイシズムの美学は日本では「受けにくい」のはサマーソニックでも思いましたし、分かりやすい大きな表現を受容する磁場がマスを設定しているのだ、とも別の解釈をするとしたら、 社会心理学者のラザーズフェルドの研究でも最も有名な「コミュニケーションの二段の流れ」説を考えてしまいます。
少しだけ難しい話を致しますと、ラザーズフェルドはちなみに、1944年のアメリカ大統領選挙でマスコミの報道と、各人の投票行動の関連についてパネル調査を行ない、その結果、事実に基づいた報道について民衆はマスコミの報道を信用していたというデータが出ますが、これらの事実をどう評価するかについては,民衆は決してメディアの出す評価に同調していなかったというのが分かります。ラザーズフェルドは、享受側の評価とマスコミの評価との喰い違いが起きるときに、どんな要因が各々の評価に影響をあたえているかを調べてゆき、身のまわりの小集団の意見がマスコミの報道以上に大きな影響を付与していたことを詰めました。つまり、逆説的にまだメディアの影響力や明瞭な存在感のカタルシスが仕掛ける受け手の感情の青田刈りには勝てないということなのかな、とも思いもしました。
しかし、だからこそ、私は彼らに期待していたのもあり、その期待は今現在も続いています。上品な翳りがあって、スタイリッシュでメロディーもタイトに締まったバンドとして、アンサンブルも「引きの美学」でいて、それでいて何処となく、厭世感と冷ややかな熱さが漂っているムード。
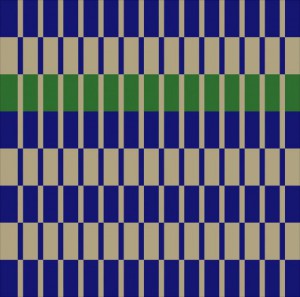 2008年のデビューEPの『Moralist S.S.』は、興味深いものでした。特に、表題曲の持つキャッチーな恰好良さと、思索的な歌詞、そして、感情のひだの内側を潜行し、内側から蹴破っていくかのようなエッジ感。当時のインタビューに依りますと、フロントマンのKENT氏の意図で「S.S.」は作家の大江健三郎氏の『日常生活の冒険』の斎木斎吉から取ったと聞きます。『飼育』、『個人的な体験』、『万延元年のフットボール』でもなく、『日常生活の冒険』というチョイスの妙。この『日常生活の冒険』は1971年の作品で、或る程度、大江健三郎氏がオブセッシヴに性的なモティーフに駆られていた時期のもので、その中で斎木斎吉は模範的なモラリストとして生きる事を予め設定されているものでした。端的な説明を加えますと、18歳でナセル義勇軍に志願したのを始めに、「当時の現代」を旅と死への誘引をベースに生き残ってゆく青年像が大江氏の盟友であった故・伊丹十三氏を参照に描かれるという、大江作品群の中では比較的、地味で、評価的に決して高いものではありません。それにKENT氏が刺激を受けたという捻じれ方に私は、「出口なき、時代を生きる典型的な若者像」をしっかり視ることができました。
2008年のデビューEPの『Moralist S.S.』は、興味深いものでした。特に、表題曲の持つキャッチーな恰好良さと、思索的な歌詞、そして、感情のひだの内側を潜行し、内側から蹴破っていくかのようなエッジ感。当時のインタビューに依りますと、フロントマンのKENT氏の意図で「S.S.」は作家の大江健三郎氏の『日常生活の冒険』の斎木斎吉から取ったと聞きます。『飼育』、『個人的な体験』、『万延元年のフットボール』でもなく、『日常生活の冒険』というチョイスの妙。この『日常生活の冒険』は1971年の作品で、或る程度、大江健三郎氏がオブセッシヴに性的なモティーフに駆られていた時期のもので、その中で斎木斎吉は模範的なモラリストとして生きる事を予め設定されているものでした。端的な説明を加えますと、18歳でナセル義勇軍に志願したのを始めに、「当時の現代」を旅と死への誘引をベースに生き残ってゆく青年像が大江氏の盟友であった故・伊丹十三氏を参照に描かれるという、大江作品群の中では比較的、地味で、評価的に決して高いものではありません。それにKENT氏が刺激を受けたという捻じれ方に私は、「出口なき、時代を生きる典型的な若者像」をしっかり視ることができました。
Obeying my steady view, I bring you down.
(「Moralist S.S.」)

その後、東京に居を移したり、メンバーの変遷があるなど混沌とした様相のまま、2009年のファースト・フルアルバム『Part of Grace』が出る訳ですが、今でも愛されるリード・シングル的な意味合いのイントロのギターの響きが印象深い「Wreckage」はあったものの、作品として向き合いますと、アレンジメントの手の内の少なさ、若さゆえの音楽語彙の少なさも影響していたのでしょう、のめり込めるといよりも、不安の要素が大きくなりつつあったのを否めなかったのは事実です。でも、京都からの上京、更にスーツで固めたメンバーがダークな世界観を小さなライヴ・ハウスでポスト・パンク的に鳴らす、そんな様はやはり、貴重だと思いました。


そして、2010年のコンセプチュアルとも感じる『Meru』には、びっくりしました。「Meru」はEPとして、6曲入っているのですが、一気にリリーズ・アンド・リメインズとしての幅を広げた内容になっていたのもあります。「MERU(メール)」という言葉には、サンスクリット語で言います須弥山という意味で、インド宗教の世界観の中で、その世界の中心にそびえ立つ山を指します。サンスクリット語とは、古代インドの有識者を対象にした 「人為語」であり、ヴェーダ語から発展し、紀元前4世紀頃パーニニによって文法が体系付けられたものであり、パーニニによって完成されたサンスクリットは、その後二回だけ補修され、二千数百年経った現在も変化していないという無比の言語であり、そこから更に意味深い「MERU」という単語を孫引いてくる辺り、意識の変化がしました。KENT氏の意図に沿って、6曲のそれぞれにストーリーが付加されており、あくまでコンセプチュアルなものではないと言っているのですが、6曲を通してこそ、見えてくる世界観もあります。例えば、リード曲の「devaloka」を通底するテーマは「無常への恐れ~仏教的世界観との出会い」といったもので、流れるコードは耽美的なものであり、メロディーも思索に潜る雰囲気といい、それまでの彼等の延長線上にある曲と言っていいものでした。「Moralist S.S.」と同じくして、ライヴ映えする曲でもあります。この曲だけでも明確に分かるのですが、リズムの重厚さへの意識的な変化であり、ニューウェーヴ的な翳りを纏い、金属的でエッジのきいたギターで駆け抜けるような繊細さからの脱却をはかったことが分かります。機会がありましたら、PVも観てほしいのですが、彼らの世界観を閉じ込めた美しいものになっています。
このEPに入っています「devaloka」や「decline together」に関しては、これは個人的な感想になりますが、世界的に今も活躍するベテラン・バンドBUCK-TICKの1995年の素晴らしい作品『Six/Nine』の持つスマートな重さ、を思い出しもしました。そもそも、BUCK-TICKの今井寿氏はリリーズ・アンド・リメインズを評価していたと聞きます。また、多方面で活躍されています浅井健一さんも真っ先にリリーズ・アンド・リメインズへの愛を示していましたとおり、派手なプロモーション展開はしなくとも、じわじわと拡がっていく瀬は感じました。なおこのEPでは、やり取り上ですが、METALMOUSEを共同プロデューサーとして参加していることもあるのか、音響空間的な幅が出ています。これまでの彼らはどこか優等生的に、紳士的に、ジョイ・ディヴィジョン的なモティーフをまっとうすることに命を賭けていたところがありますが。しかし、それが逆に、形式主義的になってしまう所は垣間見えたとも言えるのかもしれません。

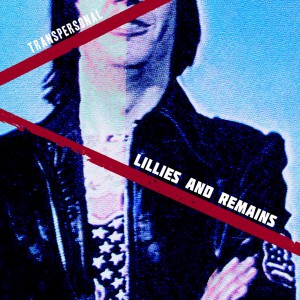 2011年にはセカンド・フル・アルバム『TRANSPERSONAL』がリリースされますが、指し示す世観は面白いものでした。アルバムのタイトル名は1960年代から起こり始めた心理学における新しい潮流のことを言い、人間性心理学における自己の「トランセンダント(超越性)」という概念に関して更に突き詰めた形のもので、昨今、隆盛しているスピリチュアル、ニューエイジ系との共振も感じさせる部分もありますが、自己を越えた何ものかへと「統合」される考えやメソッドを模索、援用するというのは『Meru』で見られたKENT氏の三島由紀夫の『豊饒の海』に刺激を受けながらも、傾いだ仏教、東洋思想(”天上”という記号性が付随していたりもした)と、その後の自身のインドへの渡航で得た「”人間としての個”を巡る再考」がはかられた結果の必然的な流れともいえるかもしれません。歌詞内でも高度なマテリアリズム、過度な個人主義社会への警鐘のフレーズなど個の超越に基づいた精神性の奪還を目するものが散見されます。例えば、「You’re Blind」という曲では以下のようなフレーズが残ります。
2011年にはセカンド・フル・アルバム『TRANSPERSONAL』がリリースされますが、指し示す世観は面白いものでした。アルバムのタイトル名は1960年代から起こり始めた心理学における新しい潮流のことを言い、人間性心理学における自己の「トランセンダント(超越性)」という概念に関して更に突き詰めた形のもので、昨今、隆盛しているスピリチュアル、ニューエイジ系との共振も感じさせる部分もありますが、自己を越えた何ものかへと「統合」される考えやメソッドを模索、援用するというのは『Meru』で見られたKENT氏の三島由紀夫の『豊饒の海』に刺激を受けながらも、傾いだ仏教、東洋思想(”天上”という記号性が付随していたりもした)と、その後の自身のインドへの渡航で得た「”人間としての個”を巡る再考」がはかられた結果の必然的な流れともいえるかもしれません。歌詞内でも高度なマテリアリズム、過度な個人主義社会への警鐘のフレーズなど個の超越に基づいた精神性の奪還を目するものが散見されます。例えば、「You’re Blind」という曲では以下のようなフレーズが残ります。
「getting out from the shell , you face the greedy people you notice that he is the man who’s living the material world」(殻を飛び出して、君は強欲な人たちに出会い、彼が物質的な世界で生きていることに気付く)
「finally you have to stand alone.i’m always watching you many times,you feel alone. but i can connect to you」(最後には 君は一人で立たなければならず、僕はいつもそんな君を見守っている 孤独を感じることが多いかもしれないが、僕は君と繋がっている)
80年代のシンセが押し出されたヒューマン・リーグ、デペッシュ・モード辺りのニュー・ロマンティックスのような華やかさからポスト・パンクの色がより強まり、ビートが更に逞しく強化されたことにより、ストイックながら拓けた印象も強い一枚になっています。当時、私はインタビューの際で「シリアスな黒い色香の漂うポップネス」というフレーズを添えていましたが、この作品はこれまでにない反響があったようで、エレクトロニクス要素が良い形でポップなエッセンスとして機能しながら、抑制されたメロディーの下、KAZUYA氏のエッジのあるギター、KOSUKE氏のアタック感が強まったドラム(※2011年9月16日にて脱退、現在はサポート・ドラマーを入れた形式になっています)、NARA MINORU氏の静かな熱を帯びるベース、KENT氏の蠱惑的なボーカルの一体感が受け容れられてきたということなのかもしれません。
2011年は、そのアルバムを持ってライヴ活動を行ない、東京の代官山UNITを埋め、SHERBETSとの共演など確実に伝播していく中で、Plastic Zooms、世界的なバンド、Purpleなどとともに、独自の磁場を作っていき、2012年2月からは新たな試みとして“MOTORAMA”という主催イヴェントを始めます。“00”ではDE DE MOUSE+his drummer、残念ながら中止になってはしまったものの、“01”では浅井健一さんのSHERBETSのみならず、UKから大御所のキリング・ジョークやセルフィッシュ・カントが予定されていました。
 ここまで書いてきた印象をして、リリーズ・アンド・リメインズというバンドに小難しさととっつきにくさを感じた人たちも多いかもしれませんが、音楽そのものは誰でも響くものです。今のところの最新作にしてカバーアルバムの『Re/Composition』では、ブリトニー・スピアーズの「Toxic」のパンキッシュなアレンジなど興味深いものもあり、原点の確認作であり、これからを見越した意志が見えます。
ここまで書いてきた印象をして、リリーズ・アンド・リメインズというバンドに小難しさととっつきにくさを感じた人たちも多いかもしれませんが、音楽そのものは誰でも響くものです。今のところの最新作にしてカバーアルバムの『Re/Composition』では、ブリトニー・スピアーズの「Toxic」のパンキッシュなアレンジなど興味深いものもあり、原点の確認作であり、これからを見越した意志が見えます。
いざ、楽曲に向き合ったときに「洋楽みたい」と言った若い子が居ましたが、そういう垣根はイメージが先走った結果の判断の決定のようになってしまう気もします。誰しも知っていると思いますビートルズは世界中に愛されていますが、それでも、相当、実験的なこともしてきました。日本語で分かりやすく歌い、伝えること。それも、アーティストの美学であり意識でしょうし、リリーズ・アンド・リメインズは英語でしっかりとメッセージを伝えようとしている、それも美学であり意識です。
私はいつも想い出す風景があります。仕事で移動中だった阪急電車でバンドをしているらしいギターを背負った高校生の男の子が必死にアメリカのグリーン・デイというバンドのCDを持ち、その歌詞をノートに書いては、ヘッドホン越しに何度も呟いていたことで、音楽とはつまりはそういうものなのかもしれない、とも思いました。音楽は国境を越えるとは簡単には言えませんが、しかし、まずは出会ってみることで、新たな扉が開いてますます音楽の持つ深みを知ることもあるものです。この原稿で軸として書かせて戴きましたリリーズ・アンド・リメインズだけではなく、今の時代ほど、多くのアーティストがオルタナティヴな活動を行ない、それを観ることができる機会が多いというのはないと思います。

最後に、リリーズ・アンド・リメインズというバンドは日本、UKでも着実に人気を得てきているバンドですが、その轍は平坦ではなく、これからも大変なことも多いと察します。それでも、フィルターがかかっていたり、英語詞で歌っている、そういったことで聴くのを拒否されているのは残念でならず、そういった意味も込めて、初期から知っている彼らのことを書かせていただきました。なので、少し難しい表現や名前だけは知っていても、というバンドなどが出てきたと思います。それでも、今の時代、現場に足を運ぶことも動画や曲自体にアクセスすることができますし、タフなリスナーは増えていますから、彼らを理解していけるのだと思います。理解までいかなくても、まずは知ってもらうこと、と言いましょうか。
KENT氏がはっきりと言う「自分たちの音楽はポップであり、オルタナティヴである」とのフレーズに沿えば、まだまだ始まってさえもいないバンドだとも思います。スタイルは違えども、ザ・ボウディーズの持つ恰好良さもじわじわと拡がったもので、リリーズ・アンド・リメインズも今、風が吹いている時期によせて、始まりの合図として、少しでも、彼らを知って戴き、それぞれの生活の中に新しい発見と、自身の心の中に新しい風が吹くものがあれば、越したことはありません。そんな少しの補助になるテクストとして機能しておりましたら、幸甚の至りです。
まつうら・さとる●1979年生まれ、大阪府出身。好きなアーティストはレディオヘッド、ブラー、スピッツ、小沢健二、くるり。現在は、東アジア経済圏域の研究員をしながら、音楽メディアCOOKIE SCENEなどを主体に多岐に渡る執筆活動も行なっています。大学を出て、一度、普通に働き、大学院にまた入り、様々な人の繋がりの中でこうして今の場所にいます。音楽が好きになったのはどんな国へ行っても、色んな生き方をしている多くの人たちの感性に訴えかけられるものだと痛感しているからかもしれません。近況としては、日本語の「美しさ」に改めて魅せられることがあり、泉鏡花や夏目漱石の一連の原著を読み返したりしています。また、豆腐や蕎麦をこよなく愛好します。