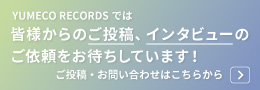2017年。またの名を平成29年。
自分史上最大級の昭和ブーム到来中です。
今回語るのは、そんな昭和の香りが色濃いシンガーソングライターの中田裕二氏。3月にリリースされた6thフルアルバム『thickness』について、先日開催されたツアーファイナルにも触れつつ、語ってゆく所存です。しかし、ディスクレビューはすでに『音楽と人』でも書いたので……。同誌にて連載中の中田裕二が呑み歩くコラム「東京ネオントリップ」と、文豪コスプレグラビアなど今回もネタ度満点のツアーパンフレット『シックネス野郎』へ、愛を込めて。着物を着込み、ツアーファイナルの舞台でもある三軒茶屋へ。純喫茶、裏路地、立ち呑みとネオントリップしながら『thickness』へ想いを巡らせて来ました。中田裕二を知っている方も知らない方も、ぜひお楽しみいただけたらと思います。
■シックネス乙女の三軒茶屋ネオントリップ~中田裕二『thickness』によせて~
出会いは彼がまだ椿屋四重奏として活動をしていた頃。それから中田裕二という音楽家は、ずっと私を虜にし続けて来た。ロックと形容するにはあまりにも湿度が高く、歌謡曲と括るにはやんちゃが過ぎる。彼らにしか作り出せない名前のない音楽。だから椿屋の解散は、当時の私にとってひとつの音楽の死を意味していた。しかし解散の2か月後、東日本を大きな地震が襲うと、彼は沈黙を破り、すぐさま「ひかりのまち」という曲をYouTubeで発表した。被災地となった宮城県は、椿屋四重奏結成の地だったのだ。震災が起きてしばらくは、当時私が住んでいた神奈川県でも停電が発生し、灯りを求めて携帯を開いては「ひかりのまち」の動画を観ていた。
すると車窓から見る民家の灯りのような、ほんわかと温かい彼の歌がこわばった気持ちをゆっくりとほどいてくれたのだ。椿屋四重奏の歌は、やりきれない気持ちやヒリついた感情を、そのまま鋭角的に放つものが大半。だからこそ中田裕二の歌を聴いて、そんな感覚になるのは初めての事だった。彼がソロシンガーとしてのデビュー作を発表したのは、それから8ヵ月後。あの大きな揺れが、彼の音楽家としての魂を否応なしに覚醒させたのだろう。今はそんな風に思う。

デビューアルバム『ecole de romantisme』から6年、ソロとしては7作目となる今作。『thickness』というタイトルが意味するのは、厚さ、濃厚、緻密……つまりは一言でいえば“こってり”だ。中田裕二と言えば、ねっとりとクドい歌声と、重箱の隅の隅までぎっちりと詰め込まれた音が特徴(バンド時代は違ったのだけれど……)。こんなにもうってつけの英単語が存在するとは。座布団1枚。しかし、実は私、前作『LIBERTY』が発売されて以来、中田裕二の音楽から少し気持ちが離れてしまっていた。ひとつ前の『BACK TO MELLOW』で歌謡曲を軸としつつ、AORやシティポップを取り入れるという方向性が確立され始め、そこから更に一歩と深めていったのが『LIBERTY』。

フォークやファンクの要素も加わり、音楽的には相変わらず多彩だったし、歌にも磨きがかかっている。でも曲たちの顔つきが、どこかで観たことのある顔をしていた。中田裕二の音楽に良く出てくる表情ばかり。得意パターンをさらに突き詰められたレベルの高い作品と言えばそうなのだけれど、私はもっとハラハラしたり、ドキドキしたりしたかった。もっと観たことのない顔をして欲しかった。だからどこかのインタビュー(たぶん『音楽と人』)で「次はロックなアルバムになる」と彼が語っていたことが嬉しくて、今作の発売は心待ちにしていたのだった。

そして発売された『thickness』。ロックなアルバムか、と問われれば、答えはノーだ。ただ、今までの中田裕二の音楽の地続きにありながらも、全く新しい作品となっていたことが何よりだった。彼は世界中の音楽をかき集め、中田裕二という才能で独自のジャパニーズ・ソウルユージックを構築したのだ。バンドを断念し、ただの“歌手”にもなりきれなかった男――迷える音楽家・中田裕二。今作ではそんな何者でもない自分や、切っても切れないルーツを包み隠さず歌にすることでソロシンガーとして、ひとつのケリを付けたように思う。そう、まるでここからソロ2期が始まるとでも言わんばかりに。以上はあくまで私の私見だけれど、この作品は中田裕二にとって大きな感情の揺れの中で生まれたことは事実だった。
アルバムの制作が行われていた2016年4月、熊本県が大地震に見舞われた。そこは中田裕二が椿屋結成前の10代を過ごした土地だった。そのショックで音楽と向き合えなくなった時期もあったという。それを乗り越えて出来上がった作品だからこそ、今作からは生の中田裕二が感じられる。斜に構えても、煙に巻いても消え失せない純粋な欲求が渦巻く11曲。こんなアルバムをずっと待っていた。

でも、本当の意味で『thickness』というアルバムが響いたのは昭和女子大学人見記念講堂で開催されたツアーファイナルを観てからだった。音源で聴くよりもずっと、『thickness』の曲たちは生命力にあふれていたのだ。それは当初中田裕二が言っていたロックの片鱗も確かに窺えるステージだった。とにかく音と歌が生き生きとしていた。正直、彼のこんなライヴをホールで観られる日が来るとは思わなかった。ソロ活動が軌道に乗るにつれ、主戦場をライヴハウスからホールへと移してきた中田裕二。会場の規模を拡げたいというのはミュージシャンなら当たり前のことだろうが、それとは別に彼にはホールに対する憧れがあった。その意気込みが彼のホールライヴを少し退屈にしていたように思う。それゆえライヴハウスで観た時の手応えをずっとずっと、越えられずにいたのだ。

けれど、今回のファイナルを観て、ようやくホールがしっくりきた。ステージと客席に同じ空気が巡る感覚があった。中田裕二のライヴハウス公演にあって、ホールになかったもの。それは“ライヴ感”だ。どうしても今までのホール公演は“披露する”というスタンスになりがちだったように思う。だがしかし、今回はそういった肩肘の張った空気が一切感じられなかった。ステージから音楽を放っては、客席から返ってくるものをしかと受け止め、それを音楽に乗せて届ける。その瞬間にしかない、リアルタイムの音楽がそこには確かに生まれていた。単に回数を重ねてホールライヴに慣れただけ、と言ってしまえばそれまでかも知れない。しかし、彼は清水浩司氏による今作のインタビューで、様々な形態のライヴを経てライヴへの想いが強くなったことを語り「人に音楽を聴いてもらって初めて『俺、生きてていいんだ』って思える」と口にした。音楽家としての自負と、音楽を他者と分かち合うことの歓びを知ったことが、彼のホールライヴを変えたのではないだろうか。
どんなにそっぽを向いても、必ず連れ戻して虜にしてくれる中田裕二という音楽家。いつまでもその手の内で、踊らされていたいと改めて思った。

■monthly Rock ‘n’ Roll vol.3 ――The Cheserasera「I Hate Love Song」
ツアーパンフレット『シックネス野郎』を手掛けた奥“ボウイ”昌史氏のTwitterにも度々名前が登場する3ピースバンド、The Cheserasera(ザ・ケセラセラ)の新曲。若手ながらも、自主企画ではLUNKHEADやLOST IN TIMEといった中田裕二と同世代バンドとの対バンを行っている。踊れるだけのロックとは一線を画した、ロマンティックで棘のある楽曲が特徴だ。また、この曲のMVでも分かるが、主人公の多くは浮かばれない男だ。そこもちょっと中田裕二と通ずるものがある。そして何よりの共通点は、色気。個人的には今最も中田裕二と共演して欲しい若手バンド。そして宍戸さんには弾き語りで椿屋の「共犯」を歌ってほしい。/span>
 イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。『音楽と人』にて毎月レビュー執筆中。当初は普通にライヴレポートを書く予定でしたが、それじゃあつまらん!と急遽思い立って、この様になりました。無茶ぶりに応えてくれたカメラマン小此木愛里に感謝。『thickness』推し曲は「愛に気づけよ」。
イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。『音楽と人』にて毎月レビュー執筆中。当初は普通にライヴレポートを書く予定でしたが、それじゃあつまらん!と急遽思い立って、この様になりました。無茶ぶりに応えてくれたカメラマン小此木愛里に感謝。『thickness』推し曲は「愛に気づけよ」。