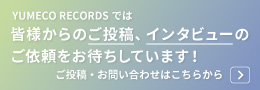好きなものに正直に、新しい「かわいい」を生み出してきた女性たちが主人公の物語「交差点のヒロイン」。
「ゴーストライターならぬ、エンジェルライター」がコンセプト。憑依するというより、守護天使のように、その人に取材し、共感をもって、物語を書きます。

今回のヒロインは、イラストレーターの田村セツコさん。
1938年に生まれ、1950年代後半より少女雑誌で挿絵やファッションページを手がけ、
『りぼん』『なかよし』『いちご新聞』などで、かわいいファッションやライフスタイルを提案する連載が一世を風靡。グッズなども当時の女の子たちの人気アイテムとなりました。
今も現役で精力的に活動を続け、その“かわいい”イラストと“おちゃめ”な生き方が、さまざまな世代の女性たちを魅了しています。
少女時代、駆け出しの時代、イラストレーターとして活躍を始めた時代、そして現在……4回にわたって、田村セツコさんの物語をお届けします。
第1話 郵便屋さん、ありがとう
▶︎第2話 苦労してこそヒロイン
第3話 締め切りが恋人
第4話 ブルーとバラ色のワンダーランド

広い社員食堂には、まだ慣れない。
「みてみて、今日はサラダがついてるわ!」
先輩が、はしゃいでセツコの肩をたたく。
ここ、人事部秘書室の社員は、この銀行の中でなぜか少しだけ特別待遇。
ランチのメニューには、いつもちょっとしたおまけがついている。今日は彩りのきれいな、小さなサラダ。
「これが毎日の楽しみだわ。いただきます」
先輩は嬉しそうに手を合わせる。
銀行なんてさぞかしお固い職場なのだろうと思っていたけれど、そこはとても楽しいところだった。
きびきびと働く、美しい先輩たち。新入社員のセツコには、毎日が刺激的だ。
「なんだか今日は食べるのが早いわね」
先輩がセツコを見て言う。
そう、セツコは急いでいる。昼休みのうちに少女雑誌の編集部へ行って、仕事のイラストを届けなくてはいけない。
「ちょっと、外へ出なくちゃいけなくて……!」
おまけのサラダをゆっくり味わう時間もなく、セツコはぱくぱくとごはんを口に運ぶ。先輩が不思議な動物でも観察するようにセツコを見ている。
かばんからはみ出した大きな茶封筒。早足で横断歩道を渡る。
――30分で戻らなくちゃ。
大手出版社のビルが立ち並ぶ神保町。このビルの中のひとつに、セツコが仕事をもらっている、少女雑誌の出版社がある。
広いフロアの一角が、その編集部になっている。いちばん奥の机は、編集長のもの。あの席で、かわいい雑誌の数々が生み出されている……そう思うと、すぐ近くにあるはずの編集長の机が、とても遠く、神聖なものにみえる。
「カット、持ってきました!」
セツコは茶封筒から絵を取り出す。
「あら、1カットの仕事なのに、10個も描いてくれたのね?」
セツコが並べた絵を見て、編集さんが言う。
「はい、この中からどれか紙面に合うものを選んでいただけたらと思いまして」
「なるほど、助かるわ。うーん、こっちのバラの図案もかわいいけれど、こっちのシンプルなほうがページに合うかもしれない。これでいくわ!」
ふむふむ、勉強になる、と思いながら、セツコは編集さんがカットを選ぶのを見ていた。ふと時計に目をやる。いけない、昼休みが終わっちゃう!
「おつかれさま」
そう言われると、大きくおじぎをして編集部をあとにする。来るときの倍の早さでオフィス街を駆け抜けて、昼休みの終わる五分前に会社に着いたときには、セツコの息は切れ切れだった。
五時、セツコは銀行での仕事を終えて、帰路につく。先輩たちと笑顔であいさつを交わして、ほっとひと息つくと、とてもおなかがすいていることに気づく。
でも、疲れてばかりはいられない。ここからが、本当のセツコの時間。
スーツからブラウスとスカートに着替え、夕飯をすませると、スケッチブックをひらく。
今日はカットを納品したから、仕事はひと段落。松本先生に見てもらうための絵を描きためてゆく。机に置いたランプのオレンジ色の光が、夜のあいだずっとセツコを包み込む。
松本先生のところには、相変わらず月に一度通っている。
そこには雑誌の編集者たちがかわるがわる訪れていて、先生はよく、その人たちにセツコを紹介してくれる。
「この子、僕のところで一生懸命、絵の仕事をしている子なんだ」
それを聞いた編集者が、ときどきセツコに仕事をくれるようになってきた。
――憧れの雑誌の仕事!
セツコにまわってくるのは「捨てカット」と呼ばれる仕事で、雑誌のページの空いたところを埋める、飾りのイラスト。そんな小さな仕事ばかりでも、セツコはひとつひとつに緊張しながら取り組む。描く手がこわばると、女の子の表情やポーズもぎこちなくなってしまう。スケッチブックに描くときはあんなにのびのびと描けるのに、仕事となるととたんにむずかしくなる。
紹介してくださった松本先生の顔に泥を塗るわけにはいかない。そう気負ったセツコは、会社から帰ってきてから夜にひたすらカットを描き、短い昼休みを使って、編集部まで届けるのだった。
昼はOL。夜――ときどき昼休み――は、イラストレーターの卵。
そんな生活も、もうすぐ一年になる。
――このままでいいのかしら……。
先輩はやさしい。安定したお給料もある。毎日が楽しくて、スリリングで、新しい体験の連続の日々。
家だってそうだ。質素だけれど、にぎやかで笑いの絶えない六人家族。
でも――。セツコの唯一の悩みは、「苦労が足りない」ということだった。
子どものときに読んだ物語のヒロインたちは、たいていみなし子で、世の中の荒波に揉まれながらさんざん苦労を重ねて、自分の手で輝く幸せを手に入れる。
今の生活に不満はないけれど、なんだかヒロインらしくない。
――苦労が足りないわ。苦労しないと、バカになる。このままじゃ、ダメだわ。
「先生、相談させていただきたいことがあるんですけれど」
セツコはかしこまって、松本先生の机の前に立つ。
「珍しいじゃないか」
忙しい先生なので、いつもは奥さまを通して先生とやりとりすることのほうが多い。弟子入りしたとはいえ、大御所の先生だ。軽々しく話しかけたりするのはためらわれる。でも今日だけは、直接話したかった。
セツコは唾をごくりと飲み込む。そして口をひらいた。
「私、会社を辞めて、絵でひとり立ちできるでしょうか」
先生はペンを持つ手を止め、ゆっくりとセツコに目を合わせる。
「そんなこと、誰にもわからないさ」
セツコははっとした。
「大丈夫かなんて、誰もわからない」
さすが松本先生だ。本当のことしかおっしゃらない方だ。
答えは私の中にしかないんだわ。セツコは口をつぐんだ。
「そうよね。誰にも、わからないわよね」
銀行の屋上から東京の街を見下ろして、セツコはつぶやいた。
流れるように現れてはビルの陰に消えてゆく車。忙しそうにどこかへ向かっている、顔のみえない人たち。
ぼんやり眺めながら、セツコはふと、ひとりの男の人に目をとめた。
しゃがんでは立ち上がり、ひとりだけみんなとは違う動きをしている。大きなカゴを抱えているようだ。
そのおじさんは、道に落ちているゴミを拾い集めては、抱えたカゴに入れているのだった。
――あの人のほうが、自由でいいな。
セツコは思った。街をひとりで歩き回って、あの人、鼻歌までうたってる。
昼休みが終わる。階段を下りるときには、セツコの心は決まっていた。
――銀行、辞めよう。
「経済的負担はかけません。弱音は吐きません。後悔はしません」
セツコは心配そうな顔をするお母さんと、顔をしかめているお父さんに、三つの約束をした。
銀行を辞めてイラストレーターになるなんて、19歳の女の子には無謀すぎるとわかっている。
「よろしくお願いします!」
大きな声でそう言って、頭を下げた。もう、誰もセツコを止めることはできない。いつだって素直だけれど、一度決めたことはゆずらない……セツコのその性格を、お母さんもお父さんも、よく知っているのだ。
「冗談でしょう!?」
辞表を提出すると、課長はすっとんきょうな声をあげた。
「ほんとに冷静なんですか?外の世界は想像以上に厳しいものですよ。時間をあげるから、頭を冷やして考え直してきなさい」
でも、セツコは至って冷静だった。
「今まで、本当にありがとうございました。とても楽しくて、有意義な時間でした。でも私、どうしてもやりたいことがあるんです」
課長がセツコに返そうとした退職届をていねいに渡し直すと、セツコは大きくお辞儀した。
最後の昼休み。
屋上で風を浴びているセツコに、先輩が言った。
「一緒に仕事ができて、楽しかったわ。これ、おせんべつ」
先輩に手渡された包みをあけると、中からかわいい山小屋のかたちのオルゴールが現れた。
「わあ……」
ネジをまわすと、やさしい音色が途切れ途切れに流れ出した。「エリーゼのために」。オルゴールの裏には、先輩の名前がゴールドの筆で書かれている。
この屋上に来ることは、もうないだろう。ここから見下ろせるあの通りを歩くたびに、きっと今日のことを思い出す。そのときに、ちゃんと笑えているように。
数日後、セツコは大きな花束を抱きしめて銀行を出た。バッグには、先輩にもらったオルゴールも。
たった一年だったけど、とても幸せな時間だった。
花束からバラを一輪抜いて、キスをしてみる。後ろから風が吹いて、花びらが一枚、飛ばされてゆく。赤い花びらは、点になって空に溶けて、いつの間にか見えなくなった。
もらった花束は、またたく間にドライフラワーになった。
セツコの仕事は、増える気配もない。ぽっかり空いた時間だけが過ぎていく。
――自由っていうのも、困りものね。
小さなカットを編集部に納品してくると、午後はまるまる休み時間だ。
編集部の近くの神保町には古本屋さんが立ち並んでいて、そこには珍しい、海外のモード雑誌を扱う雑誌専門店がある。『ELLE』や『20ans』、定価で買うととても高い雑誌が、そこではとても安く手に入る。交通費ほどの原稿料を握りしめ、セツコはお気に入りの写真が入ったとっておきの一冊を選んで買う。
蜃気楼がかかったようにぼやけた写真。ふわっと風が吹いているような写真。文字が斜めにレイアウトされたページ。文字の一部にだけ赤色が使われて、それ以外がモノクロのページ。どれも真新しくておしゃれなものばかりで、見ているだけでわくわくしてくる。
集めた雑誌の好きなページを切り抜いて、セツコはスクラップブックをつくっている。
神保町には名画座もあって、フランス映画を三本立てで上映してくれる。ゴダールやトリュフォーのおしゃれな映画を観ると、胸が高鳴った。「女は女である」のアンナ・カリーナがとくにセツコのお気に入り。オードリー・ヘプバーンのドレスや、パリジェンヌの普段着を見るのもわくわくした。セツコは映画を観ては、スケッチブックにヒロインの絵を描いたり、ファッションのヒントを書き留めておいたりする。
そうやってひとりぽっちでさまよう時間が、いちばんの勉強の時間なのだ。
ぶ厚いスクラップブックと、色鮮やかなスケッチブックばかり、何冊もたまっていく。セツコの部屋は、ノートと雑誌でごったがえしていた。
それなのに相変わらず、イラストの仕事は間に合わせのカットばかり。
セツコのスケッチブックの中のかわいい女の子たちは、世に出るチャンスももらえないままだ。
――憧れていたお仕事って、こんなものだったのかしら。
小さなカットの納品が済んで、神保町の交差点にぽつんと立ち尽くす。
――銀行を辞めるとき、みんなあんなに止めてくださったのに……やっぱり私、生意気だったかしら。
涙がぽたりと落ちる。そのとき、誰かがセツコの肩に手をおいた。
「大丈夫ですか?」
セツコはあわてて涙をぬぐう。
「いえ、なんでも……」
十字架のネックレスを下げた、穏やかな顔の女の人だった。
「近くに救世軍の本部があるんですよ。一緒に讃美歌を聴きにいらっしゃい」
「えっ?」
痩せてふらふらのセツコは、流されるままに救世軍の本部へ入る。
十字架のついたビル。広いチャペルのような場所で、大きな音で讃美歌が流れている。
――そういうことじゃ、なかったんだけど……。
少しだけ笑えてくる。讃美歌の音が、ぼんやりとセツコを包み込む。
窓ガラスに映る自分を見やると、やつれてひどく疲れた顔をしている。
――あらあら、かわいそうに。私がなんとかしてあげるね。
セツコはもうひとりの自分に、心の中で強くそう語りかけた。
――これが、いわゆる苦労というものかしら。だったら、ずっと憧れていた苦労ってわけね、ふふ。
もうひとりの自分が笑う。ヒロインになるための第一歩、きっと踏み出している。
「おかえりなさい。お仕事どうだった?」
夕飯をつくっているお母さんに、セツコは笑って返事をする。
「うまくいってるわ!」

次回の「第3話 締め切りが恋人」は6月15日に更新予定です。お楽しみに!
 大石蘭●イラストレーター・文筆家:1990年生まれ。東京大学教養学部卒、東京大学大学院修了。在学中より雑誌『spoon.』などで執筆。伝記的エッセイ『上坂すみれ 思春期と装甲』や、自伝的短篇『そんなお洋服ばっかり着ていると、バカに見えるよ』などを手がけるほか、著書として自身の東大受験を描いたコミックエッセイ『妄想娘、東大をめざす』(幻冬舎)などを刊行。現在もイラスト、文章の執筆を中心に活動中。(photo=加藤アラタ)
大石蘭●イラストレーター・文筆家:1990年生まれ。東京大学教養学部卒、東京大学大学院修了。在学中より雑誌『spoon.』などで執筆。伝記的エッセイ『上坂すみれ 思春期と装甲』や、自伝的短篇『そんなお洋服ばっかり着ていると、バカに見えるよ』などを手がけるほか、著書として自身の東大受験を描いたコミックエッセイ『妄想娘、東大をめざす』(幻冬舎)などを刊行。現在もイラスト、文章の執筆を中心に活動中。(photo=加藤アラタ)■HP : http://oishiran.com
■ブログ : http://lineblog.me/oishiran/
■Twitter : @wireless_RAN