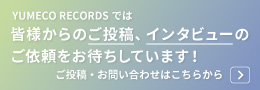解散してしまったバンドの復活ライヴというものを観に行ったのは、今回が初めてだった。もちろん、ライヴを行うバンドによって感じるものはそれぞれ違うと思うが、だいたいは復活した事への多幸感に包まれた、誰もが涙するようなエモーショナルなステージなのだろう、と予想していた。
しかし、このsyrup16gの復活ライヴは、決して安易な言葉でまとめられる内容ではなかった。これは、メンバー一人一人が今日を迎えるまでのドキュメンタリーであり、ツアータイトル『再発』という名の通り、syrup16gとして再び歩む道の「道標」となるこのステージを、この会場に集まったオーディエンス一人一人も確かめていくようなライヴだった。
SEが鳴り止み、訪れた沈黙と同時に五十嵐隆、キタダマキ、中畑大樹の3人が現れる。二階席の一番奥まで埋め尽くされたオーディエンスからの盛大な拍手と歓声が上がる中、それを崩していくかの如く、中畑のドラムが聴こえる。syrup16g、6年ぶりの最新アルバム『Hurt』の一曲目「Share the light」が始まると、場内の空気は一気に緊迫したものとなった。真っ赤なライトをバックに、五十嵐隆は歪んだエレキギターを奏で、どこか不安げな歌声を放つ。しかし、そこにキタダの安定した低音が重なれば、紛れもなくsyrup16gの姿があった。
3ピースのシンプルなバンドアンサンブルは、威圧感と生々しさでホール一体を塗りつぶしていく。
五十嵐は、多少テンポが走ろうが、言葉に詰まろうが、ギターを弾く手を止めず、ただひたすらに歌い続けていた。ステージに立った彼は、決して恰好良い自分を見せようとはしない。嫌になるくらい、見えない答えを探し続ける情けない自分をさらけ出している。ギターをかき鳴らし必死に歌うその姿を観ていると、やはり五十嵐にとって、自分を開放できる唯一の手段が音楽であり、バンドなのだろうと気づく。そして、syrup16gを再開させた理由の全てを、物語っているように感じた。
また、ライヴが進んでいくにつれ、五十嵐の声はどんどん力強くなっていく。久しぶりに大きなステージに立つことへのプレッシャーや恐れを手放すことができたのか、自分の内側にある感情の全てを吐き捨てることで、聴く者の心の傷口に自身の抱えた痛みを重ね合わせていくようだった。だから私は、何度も何度もその姿に目を潤ませることになってしまう。
そして、キタダと中畑からは、syrup16gとしてステージに立つことの強い意味を見せつけられた。
二人は『Hurt』というアルバムを通じて、バンドの再始動を決心した五十嵐の持つ唯一無二のメロディセンスと、メロディの美しさに相反するやるせない言葉たちから、syrup16gへの「情熱」を再び感じ取ったのだろう。
今の彼らが演奏する解散前に発表された楽曲たちは、6年間の空白を感じさせないどころか、五十嵐の情熱に更に上乗せするかのように新しいエネルギーが注ぎ込まれ、確実に進化させていた。これはもう、それぞれが重ねたキャリアによって凄まじい演奏を見せたのではなくて、五十嵐のsyrup16gへの想いが二人の心を動かし、キタダと中畑自身のsyrup16gの想いが音となって現れたとしか言いようがなかった。腹の底から突き上げるようなダイナミックなビートを叩き続ける中畑のドラムも、切なさをどこか心地良く響かせるキタダのベースも、五十嵐を支え、寄り添うためだけに存在していたのだ。
それは、アンコールが始まる前だった。中畑に「二階、二階」と促されると五十嵐は顔を上げ、二階席のオーディエンスに向けて「ありがとう」と手を振った時、周りを見渡す余裕もないほどに集中し、本当に必死だったことがひしと伝わってきた。しかし、ライヴ中には、一曲一曲終わるごとに割れんばかりの拍手が起こり、「五十嵐、おかえりー!」という喜びの声も多く上がっていた。復活を待ちわびていたオーディエンスの愛情で溢れかえっていた2014年9月22日、東京国際フォーラムのステージは「夢」ではなくて「現実」だったのだ。
約二時間のステージはあっという間だった。五十嵐は全て終えお礼を述べると、ロウソクの炎に「ふっ」と息を吹くと一瞬で消えてしまうあの瞬間のように、ささっとステージを去って行ってしまったが、今、私の心には爽快感だけが残っている。なぜなら、感慨に浸るわけでもなく、潔くライヴを終わらせた3人には、syrup16gの未来を予感させるものがあったからだ。そして、歌う前に「あんまり好きじゃない曲をやります」と話してはいたものの、五十嵐はがむしゃらにアコースティックギターを鳴らし<最低の中で/最高は輝く>(「旅立ちの歌」)と歌い、今の自分の居場所を肯定できたことで、確実に何か手応えを得たと思うのだ。だから、きっとまた再会を果たす事ができる。この日、集まったオーディエンスの誰もがそう確信したに違いない。
最後はその潔さを見習い、余計な言葉で飾るのをやめ、敢えて簡素な言葉で締めよう。
「本当に素晴らしいライヴだった」。
北島 祐子●30代OL。高校生の頃からロックを聴くようになり、