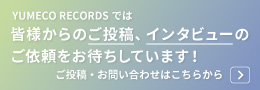「うたうともだち vol.4」KONCOS(古川太一&佐藤寛)
歌い手の友達同士で繋いでいく本連載、「うたうともだち vol.4」。今回は、前回ご登場いただいたシモリョーさん(the chef cooks me)からご紹介いただき、KONCOSのお二人にご登場いただきます!今までは別々のバンドやソロで歌っているシンガー同士の対談でしたが、今回は古川太一さんと佐藤寛さんからなる二人組ユニット、KONCOSへとバトンが渡りました。
二人は高校時代に北海道・帯広で出会って以来の友人で、地元の仲間達と東京で結成したバンド、riddim saunterで活躍した後、KONCOSとして再出発しました。現在は「旅」をテーマに日本中を旅しながら、日本語と日本の景色が響く歌を届けています。そんな彼らだからこそ、私たちも旅をしながら取材したいと思い、昨年「旅するコンコス 帯広篇 ~コンコスと行く、秋の北海道~」にお邪魔してきました。後日、東京でインタヴューしたテキストと共に「うたうともだち vol.4」、お届けいたします!
(文=上野三樹 撮影・取材協力=伊藤佐和子)
——今回はシモリョーさんにご紹介いただいたわけですが、彼とは長いお付き合いなんですか?
古川「前にやっていたバンド(riddim saunter。以下リディム)の時からだから、もう10年くらいですね。最初に対バンしたのは、熊谷のHEAVENS’ROCKで、たしかavengers in sci-fiとthe chef cooks meと対バンで誘われて。なんとなく同い年で、なんとなく下村くん(シモリョー)もひねくれたポップス好きっていうのが合って(笑)。なんかそういうので仲良くなっていって、バンドが解散してからも誘ってくれたりして」
——リディムとしての活動は結構長かったですよね。(2002年結成。2011年9月3日、中野サンプラザにて行われた”FAREWELL PARTY”をもって解散)
古川「そうですね。アルバムも3枚出しました」
——リディムと、今やってらっしゃるKONCOSは、活動形態も音楽性も全然違って面白いですよね。
古川「音楽性自体が変わっている意識はないんですけど、多分、中身は全然違うかなと思います。前はふんわりなんとなく“良い曲かな”と思って作っていたけど、今は以前より歌に重点を置いているような気がしますね。前も“いいメロディを作りたい”と思って作っていましたけど、歌詞が英語だったので、海外に寄っていたと言うか。今の方が日本語詞を重要だと思っていて…重要というか、“面白くしたい”っていう意識がありますね」
——古川さんと佐藤さんが出会ったのはいつですか?

やってきました帯広駅!!
佐藤「僕は生まれも育ちもずーっと帯広なんですけど、太一は中学生の頃に転校してきたんですよ」
古川「僕は福島の郡山出身で、中学校の時に帯広に転校してきて。高校で同じクラスの人たちとバンドを始めて、啓史(田中啓史 ex.riddim saunter/現在はKeishi Tanaka名義でソロ活動中)も同じ学校だったから、そこでriddim saunterの母体が出来て」
——高校時代はどういう遊びをしていたんですか?
古川「バンドと、あと僕はDJをやっていたので、夜はクラブで遊んでました。寛は家がちょっと遠かったんだよね」
佐藤「家に帰る最終バスが夜9時くらいだったから、それまでには帰ってましたね。それを逃すと帰れなくなるから(笑)」
古川「帰れなくなったら帰れなくなったで、うちや啓史の家に泊まったり、夜まで遊んでいました」
——通われていた高校は、進学校で制服が無くて、けっこう面白い方が集まる学校だったと聞きました。
古川「そうなんですよ。とても個性的で。私服だったからみんなの素が見えるし、それが良かったと思いますね」
——オシャレは意識していましたか?
古川「毎日私服だから、自然と洋服は意識するようになりました。元々好きな人も多かったのかな。あとはヒップホップの影響が大きいです」
——DJは郡山時代からやっていたんですか?
古川「いえ、音楽を好きになったのは帯広に来てからですね。帯広の先輩たちに飛び込んでいって」
——帯広で音楽にのめり込んでいくというのは、町の背景として何かあったんですか?
古川「最初は、すごくアンダーグラウンドだったんですよね。ヒップホップは。その時は、今札幌で活躍しているMic Jack Productionの前身のラッパーズロックというグループや、僕がラジオから最も影響を受けたDJ SEIJIさんとか、もっと上の方たちが帯広に出入りしていて、教えてくれた文化があって。それでライブハウスと繋がっていっていうのが面白かったんです。そのライブハウスは途中で一度なくなってしまったんですけど、そのあと今のRestになりました」
——最初の音楽の入り口はバンドではなかったんですね。
古川「そうですね、ヒップホップとDJです。僕と寛が最初に飛び込んだ時は、ちょっと危ない感じが多くて、バンドだったらロックだけじゃなく、ロックにファンクの要素やジャズの要素などがミックスされているようなバンドとか、聴いた事も無いような変わったバンドが多かったです、あの町は」
佐藤「高校で出会った時にはもう、太一はそういうところに出入りしていたから、連れて行ってもらって。僕が住んでいたのは本当に田舎で、周りはみんな農家だったから、初めは衝撃的でしたね」
——景色がガラっと変わったわけですね。
古川「そういったヒップホップの文化が入って来ていたりして、すごく恵まれた環境だったと思います。僕はそれで作られた。バンドをやり始めたのは、僕の中では結構あとのことで。僕にはまずヒップホップがあって、ファンクの波が来て、周りにはハービー・ハンコックやクール・アンド・ザ・ギャングのカバーをやっている人たちが居て……最初にそれが基礎にあるから、もしかしたら今やっていけているのかもしれないとすら思います。面白かったんですよ、最初の帯広はすごく悪くて……危ない感じがして、だからワクワクするっていうか。若いやつがそこに飛び込むのが面白いわけですよ」
——なるほど。刺激を求めてというか、最初は遊び場としての音楽だったんですね。
古川「すごく行きづらい場所だったんですよ、入りにくくて。そういう感じが面白かったんでしょうね。もちろん実際には全然いい人ばかりなのですけど(笑)。未知の世界、みたいな。全然知らない事が地下で起こってそうなヒップホップの感じに惹かれたんですね」
——佐藤さんは音楽に出会うまで、退屈していた部分もあったんですか?
佐藤「確かに高校生になるまでは、周りに音楽を聴いていて話が合うっていう人はいなかったから、ひとりで聴いていましたね。僕はずっと野球部だったんですけど、冬は雪が降って野球ができないから暇だなと思っていて。週刊少年ジャンプとかの裏表紙に載っている“激安17点セット!”みたいなの買って、ギターを始めました」
古川「冬は身動きとれないもんね」
佐藤「そう、だからみんなスキーとかに行くんですけど、僕は苦手だったから」
——ひとりで音楽を聴いたりギターを弾いたりっていう時間がありつつも、なかなか話が合う人には巡り会えないでいたんですね。
佐藤「本当に小さい町だったので。帯広空港に行く途中のような感じで、周りは畑だけで」

帯広空港からのバス車内にて、 どーんと広がるこの風景!
——ああ!でも、すごくいい景色でした。じゃがいも畑が広がっていたりして。ご実家も農家なんですか?
佐藤「元々は農家だったんですけど、今はやってないです」
——かたやアンダーグラウンドなヒップホップが展開されている場所と、のどかな大地と。
古川「不思議な場所ですよね、帯広って」
——コントラストがすごいですね。そんな町でリディムの母体が発生して、高校を卒業して上京してから活動が始まっていくんですね。
古川「その間もすごいブレましたけどね(笑)。色んな要素を取り入れすぎてしまって」
——すごく色んな音楽を聴かれているなかで、ひとつの音楽を紡いでいく。10年近くの活動を経たあとで、お二人でKONCOSとしてやっていく、となったのは、どうしてだったんでしょうか。
古川「もともと僕は、曲を作ってはいたんですけど、ギターも弾けないしなんにも出来ないから、どこかなんとなくになってしまっていて。それが嫌だったし、ピアノで曲を作りたいっていう想いもあってピアノを始めたんです。バンドが解散して、また曲を作るかってなった時に、ピアノとギターで色々カバーを始めたのがキッカケで、初心に戻って」
——バンド活動を辞めようとなったあたりから、曲作りへの欲求が変化したんですか?
古川「そうですね、それまでも曲は作っていたけど、自分で演奏できないのがコンプレックスだったんです」
——ずいぶん大胆な転向ですよね。コンポーザーとして曲を書き、パートも変えずにいくっていうことも、多分出来たじゃないですか。
古川「うん、でも、まあいっかなって(笑)。ピアノが弾きたかったから。それに思い切っちゃわないと、出来ないことだったと思います」
——何歳でピアノを始めたんですか?
古川「もう最近ですよ、解散した年だから…29歳ですね(笑)。今始めないと、もうだめだって思って。もちろんバンドの頃からちょっとは弾いてたんですけど、そんな弾けるなんて言えるものじゃなかったから」
——そこでどうして佐藤さんが歌うことになったんですか?
古川「なんでだったっけ。最初は寛がソロでやることになったんだよね?」
佐藤「バンドが解散したあとに、僕がソロでライブに誘ってもらって、やろうかなと思ったんですけど、ソロでなんてやったこともなかったし、ひとりで歌うのもなあって迷っていて。ちょうど太一とスタジオに入ったりしてたので、じゃあ、ってふたりでやることにして」
古川「僕がピアノを弾くことにして、トッド・ラングレンだったり、ロジャー・ニコルズやポール・ウィリアムズのような、“ザ・ポップス”のカバーをやっていたんです。美しいコード進行をピアノで研究して、今度は作りたくなったっていう経緯ですね」
——そもそも前から歌いたい欲はあったんですか?
佐藤「いや、特になかったです。今も自分がどうしても歌うっていう気持ちはそんなにないんですよ。二人しかいないから、二人で成立させるためにはなるべく何かをやったほうがいい。僕はギターを弾くし太一はピアノを弾くからとりあえず手は埋まっている。口はふたりとも使えるから、使えるものは使った方が良いって。あと、太一と比べて、どちらかというと僕の方が歌向きの声だったっていうのがあるのかな……」
——そんな消極的な理由で(笑)。
古川「やってみたら意外といけるじゃんってなって、それから僕がピアノを練習してピアノで曲を作れるようになったり、ギターをベースにコードを作っていって、じゃあこれに日本語を乗せてみようとか、ハーモニーをつけてみようってやってみて。僕は元々コード感を出してハモりを付けるのが好きだったので、もっとそういうのを試してみようってやっていって、段々とスタイルができていきました」
——今までもバンドでコーラスをやる機会はあったと思いますが、こうしてメインボーカルといった形でやることになったり、大人になってから鍵盤を始めてみたり、ある意味これまでのキャリアを一度リセットした感じですね。
古川「キャリアゼロの初心者になっちゃいましたね。あんなに色々練習したのに(笑)。でも、その方が新しいものが作れるかなって」
——先ほどは歌に重点を置いているとおっしゃっていましたが、KONCOSの楽曲はコンセプチュアルだと思うんですよ。
古川「そうですね。歌と歌詞と活動のすべてに繋がりがあるから面白いですよね。“日本”というものに重点を置いているんです。何を言っているかがわかるとか、何を歌っているかとか、そういうのが出来るだけわかる方が面白いかなって」
——それこそ今では、子供も一緒に歌えるメロディだったりして。
古川「誰でも歌えるけど、コードがちょっと変わっているとか、簡単なだけじゃなくて、ちゃんとこう、響く部分をどういうコードにするかとか、そういうのを考えるのが面白くて」
——バンドでやっていた頃の、カジヒデキさんやチャーベさんのような、人との繋がりで一緒にライブをやる機会も多いですよね。
古川「ふたりだからこそ、色々なことや色々な人とやる可能性が広がっています。誰かに入ってもらうのも、誰かのところにくっつくのも身動きがとりやすいという部分もあります。例えばカジさんだったら、ドラムとギターでサポートしたり、僕が鍵盤弾いたり。僕らの曲は基本的にピアノと歌で成立するよう作っているので、どんどん足すことが出来る。でも、まず二人の状態で楽しめて物足りなくないように作っていて。そのためには、歌と歌詞とコードとテーマが重要なんです」
——こういうシステムにした一番の理由はなんだったんでしょうか。
古川「シンプルなものがやりたくて。ピアノとギターで、日本語で、意味が分かって、良いメロディーという」
——もっと伝えたいと思った?
古川「そうですね。何を伝えたいかっていうと、一番は“日本は面白いよ”ってことなんですけど。なんだろうな…日本だったり、地元だったり。帯広のことを歌ってみたりすると、嘘がないじゃないですか。自分が居たところのことを歌うっていうのはフィルターがかかっていなくて、そのまんま出てくるから」

この日の会場は〈北のれんが 古柏堂〉。築90年の素敵な佇まい。
——なるほど。KONCOSが始まってもう2年くらい。旅をしながら音楽をするっていうのも重要なテーマですよね。
古川「はい。旅をしながら続けています。47都道府県を回ったっていうのも大きかったですね。最初に帯広をテーマにしてみたことで、日本を全部回ってみようかってことになって。それはずっと夢ではあったんだけど、東日本大震災があった以降だったし、色々と今のうちに見ておかないといけないものがあるだろうと思って始めてみたら、実際知らない事ばかりで。気づかなかったことだらけでしたね。それが1stアルバム『ピアノフォルテ』以降、今のKONCOSのスタイルに繋がっています。もっと色んなところを見に行くと広がって行くだろうな、と思っています」
——しかもライブをやっている場所も普通のライブハウスだけでなく、結構ユニークですよね。

東京からウーピーゴールドバーガーやピリカタント書店が出店し(スタッフも帯広出身の仲間たち)、開演前から賑わいます。
古川「修業になりましたね!カフェとか幼稚園とか、お客さんも小学生だけの時もあったり、形態が色んなことになってきて。ステージには僕らふたりしか居ないから、ライブ中も喋らないといけないじゃないですか(笑)。だから本当に崖っぷちみたいなツアーで、全部初めてみたいな。人前で喋ったことも歌ったこともなかったようなふたりでいきなり行くわけですから、修行ですよ」
——なるほど(笑)。MCの雰囲気もすごい独特で、お二人で話しているようで佐藤さんが相づちを打ってはいるんだけど、古川さんが一人で完結しちゃうっていう(笑)。
佐藤「それも、47都道府県を旅するうちに、段々と確立されていきました(笑)」


古川「最初の頃、何も喋らずにやってみたら30分くらいで終わっちゃったんですよ。これはまずいと思って、ちょっとずつ曲の説明をしながらやってみて。どういうスタイルになるのかなあと思っていたら、こうなりましたね」
——佐藤さんはあまり話されないんですね。
佐藤「そうですね、普段からこんな感じですね」
古川「昔からずっとこんな感じです。実は、ライブと普段であんまり変わらないように、フラットにしたくって」
——肩肘を張っていないというか、すごく自然体ですよね。
古川「それこそお客さんと接する時も、全部一緒。すべてフラットに置いた時に、どういう風に考えられるかなとか」
——そういう意味でも、これまでとKONCOSでは提供しているものやコミュニケートの仕方が全然違いますよね。それこそリディムのライブではフロアでキッズが暴れていたのが、今では小さい子も手を叩きながら一緒に楽しんでいたり。
古川「そうだったらいいですよね。けれど、子ども目線で音楽をやっているという意識はなくて。だからこそ彼らにもグッと来るんじゃないかなと。子どもだからこれでいいんじゃないかとか、子どもを下に見るようなことは絶対にやらないから。だから小学校でやらせてもらった時もちゃんと会話が出来たし。ゆきが降って積もる様子を音に表した「ふるつもる」というインスト曲を聴いてもらい、各自が曲を聴いて感じたままを絵を描いてもらうという事をやってみたり」
——子どもの目線に下るのではなく、ちゃんと音楽の面白さを伝える。だからこそ幅も広がっていく。
古川「子供は真剣だから対等に話したい。だからこそ面白いし、気が抜けないんですよね」
——佐藤さんは活動の中で、歌う喜びを徐々に感じるようになりましたか?
佐藤「歌うこと自体は昔から好きではあったので、すごく楽しいですね。始めたばかりの頃はライブ前に緊張でお腹痛くなったりしてましたけど(笑)」
古川「47都道府県ツアーに出る前は本当にやばかったよね。何もできなかった。僕ら目当てのお客さんは僕ら二人の奥さんだけで、セッションのライブとかなのに緊張しているんですよ(笑)。今まで何百回ってライブしてるのに」
——そのくらい、丸裸になった感じだったんですね。
古川「裸ですよ、パンツも穿いていないような…。今まで本当に何をやっていたんだろうって思ったくらいです。それもあって、修業ってことで47都道府県ツアーに出たっていうのもあります。人前でやるのが一番の練習になるから、人前に立つ回数を増やさないとダメだって、とにかくライブをやろうって」
——それで鍛えられて、お腹痛いのもなくなって。
佐藤「治りましたね(笑)」
——本当におふたりのハーモニーって独特で、両方ともファルセットというか、すごく繊細なものに繊細なものを重ねている感じがするんです。そういうところも意識しているんですか?
古川「ロジャー・ニコルズとか、ソフトロックといわれるハーモニーが豊かなロックやAORやソウルが好きで、そんなハーモニーがやりたくて、メロディーに僕がうまくハモってみたのが最初。やっていくうちに慣れてきたので、最近ではもう意識はしていないんですよ。ピアノを弾いていたらだんだん音が取れるようになってきて」
——発声の面では最初と特にスタイルは変えていないんですか?
佐藤「元々があまり歌っていなかったのが、どんどん歌うようになったので、喉や声がもつようになったっていう変化はありました。最初はすぐに酸欠になってフラフラしてたんですけど(笑)。今はふたりとも、単純に歌えるようになったというか、身体的にもかなり鍛えられましたね」
古川「僕は歌が上手いわけじゃないんですけど、上手い下手じゃなくていいかなと思っていて。寛は良い声だと思うからメインボーカルで、僕の声は素材っていうか。あとは、僕とかが歌っていたら“あいつでも歌えるんだ! ”って勇気づけられるじゃないですか(笑)。だからそんなに上手くなくてもいいじゃん、って。どちらかというとメロディーの高揚感とかで表現できればいいって思ってます」
——やっぱりおふたりにしか出せないハーモニーがあるように感じます。
古川「それは嬉しいですね」
——でも酸欠になる、って(笑)。
古川「いや、本当に最初の頃は大変でしたよ。リハーサルも1曲でへとへとになっちゃって!」
佐藤「その頃はボーカルの人って本当にすごいんだなって思いました」
古川「尊敬しました、Keishi Tanakaを……」
佐藤「あんなに動いてね……。やってみないとわかんないね」

——旅をしながら、歌っていくことが今は一番大事なことですか?
古川「見たことのないものを見に行くのはレコードとかとも同じで、あとは会ったことのない人に会うとか、訪れた場所の地元の人の話を聞くことハッと気づかされたりして、次の音楽の参考になるんです。最近はそんな頭の使い方をしながら生きています。だから気が抜けない。とにかく地元を大事にしたいですね。なるべく行けるところにどんどん行きつつ、帯広でももっと何かが出来ればいいんですけど」
——先日の帯広のライブの曲順でも、日本一周しながらまた帯広に帰ってくるというストーリーがありましたが、KONCOS が伝えたい “帯広の良さ”ってどういうところでしょうか。
古川「地元の事を落ち着いて考えてみると、素晴らしい街だなと思う事がたくさんあって。ルーツをしっかり持つことが重要かなと思っていて。あとは、旅を通して見て来た中で、地方都市に元気がなくなる理由が少しわかってきた。やはり東京など、大都市中心になり過ぎていているのかな、とも思ったのです。僕らが帯広をテーマにしているのは一つのパターンであって、例えば鹿児島であったり和歌山であったり、みんなが地元だったり、興味を持った街を盛り上げて行けたら、もっと良い方向に進むんじゃないかなと思っているんです」
——KONCOSを始めた頃に震災があったということも、関係している?
古川「そうですね。僕の出身地でもある郡山、というか福島は、浜通りの一部が原発事故で立ち入り禁止になってしまって。それで一度考えて、これはどういうことなんだろう、って、今の日本における状況というか、ずっと前から気になっていたことなんですけど……、大型の商業施設などが出来て、どこの街の風景も変わらなくなってきたり、お店がどんどんチェーン店に変わっていってしまうことだとか、ずっと思っていたことは何なのかなって考えながら47都道府県を回ると、自分たちの身の振り方というかやり方がわかってくる。街の喫茶店に行ったり、地元に根付いた居酒屋に飲みに行ったり、大衆食堂を探して飯を食べたり、そういう事が今の状況への小さな反抗だったり。そういうちょっとしたことを、みんなが気付いていったら変わるかもしれない。そして、日本をちょっとずつ隅から動かしていくような頭の使い方は、たとえば被災地だけじゃなくて、日本各地の街でやって行かないと変わって行かないと思う。そして自分の街にしかないものをきちんと知る。そうすると自分の街が楽しくなってくると思います。例えば大型ショッピングモールって、便利だけど、そういうことだけじゃない楽しみ方をどんどん見つけて行かないと、つまらなくなっちゃうから」
——まさに全国47都道府県をツアーでまわったミュージシャンが、MCで「休日はどこで遊ぶの?」と聞いたら、そうしたショッピングモールの名前が全国色んな場所で返ってくるとおっしゃってました。
古川「僕も何も考えずに生活していたらそうなるかもしれない。どこに行っても同じラインナップでショップが展開されているじゃないですか。僕が郡山に住んでいた頃、チェーン店のドラッグストアが出来て地元の薬局がダメになったりしていた。やっぱり人は安い方に行くし、チェーン店にも良い部分があるから、地元のお店だって人が来るような工夫をしないといけなくて、両方とも考えないといけないことだと思うんですけどね」
——その街にしかないものをちゃんと愛すっていうか。
古川「そうですね、それが面白いと思うんですよね。そういう再発見の一歩として、僕らが僕らの地元に向き合うことが始まりだったんだと思います」
——私も今回の取材で初めて帯広を訪れたんですが、同じ北海道とはいえ、札幌とはまた全然違うんだなと思いました。
古川「ライブをきっかけに、そうやって帯広に来てくれたことも嬉しかったです」
——もしご出身が札幌だったら、きっとまた違ってましたよね。
古川「札幌に比べたら小さな街だし、欲しいものがすぐに手に入らないのが良かったのかもしれない。その時、僕は何でもある都会に憧れていたから…。都会で10年くらい生活して、今改めてよく見てみると、なんかいいなあって。帯広、うまいものあるし、水綺麗だし、空気綺麗だし、景色綺麗だし。でも、東京は東京で僕がまだ知らないだけでウマいもんがいっぱいあるから、まだまだやる事がたくさん、帯広も東京も行きたいお店だらけです」

美味しいジンギスカンが1人前360円!!
——帯広で行った焼き肉屋さんでジンギスカンが360円だったんですよ……。
古川「そうそう(笑)。まだまだ良いお店たくさんありますよ、今度来る時は教えますね!」
——私は福岡出身なんですけど、帯広の町を歩きながら、上京してくる前の気持ちになったんですよね。あの時だったらどんな風に思ったかなとか、どこで働こうと思ったかなとか色々考えていました。就職するなら六花亭かなとか(笑)。

六花亭の本店には喫茶スペースがあり、ホットケーキやチーズケーキをいただけます。
古川・佐藤「(笑)」
古川「僕らは今30ちょっとなので、僕らと同じ世代の人たちがこんな活動に面白みを感じてくれたら、居酒屋に行く時もお店を選んだり何のお酒を飲むかの目線もちょっとずつ変わるじゃないですか。もっと若い世代は単純に音楽を楽しむところからでいいし」
——音楽が好きな人が旅をしながらライブを楽しむっていうこともいいことですよね。
古川「リディムのお客さんが昔からそういう楽しみ方をしてくれていて、そこからヒントをもらったところもありますね。いいなと思ってました」
——その土地ごとで聴く感じも違ってきますよね。
古川「絶対違うと思います。そういうことの提案でもありますね」
——音源自体もパッケージとしてすごく良いものなので、聴いて欲しいなと思いました。
古川「そうですね。それはでも、あとからついてくるかなって(笑)。売れたら売れたで嬉しいけど、それよりもまずどこに行って何をやるかが重要。音源をつくる、レコーディングをするの前に、ライブや活動内容を優先している。そこに行って、何を見たかを、自分たちのフィルターを通して音楽で表現する。そして出来た曲をレコーディングするというシンプルな事です」
——そういう、色んな景色が入っている曲を1曲でも多く残していきたい?
古川「そうですね、そのために今活動しているようなものですね。だから、結構面白いですよ!」
——だとすると、例えば福岡なら博多より小倉のあたりとかどうですか?
古川「小倉はね、今ちょうど調べているんですよ!教えてもらったりして行きたい居酒屋が揃ってきていて。すごい興味あります。鳥栖とか久留米とかも興味あるし、都市部から外したところの良さというか、そういうことをみんなも分かってくれたらいいなと思います」
——佐藤さんはどうですか?
佐藤「多分今言ったようなことだと思います(小さい声で)」
一同・笑
——今回のインタビューの発言回数も、まさにライブでのMCの比率と同じくらいになってますけど大丈夫ですか(笑)。
古川「だいたいこんな感じです(笑)」
——いい組み合わせなんですよね。相性も性格的にも。
古川「そうですね、ふたりとも喋っていたら曲が進まないですからね(笑)。バーテンダーと客みたいですよね。僕が酔っぱらった客で。ちょうど寛の職業もそうだしさ」
佐藤「そうですね、聞いている、っていう感じですね」
——お二人の付き合いもだいぶ長くなってきましたね。KONCOSはライフワークとして、ずっと続けていける形態ですよね。
古川「まさにライフワークと思ってやっていきたいです。まだまだ続いていきます」
——今日はどうもありがとうございました。KONCOSの独特な活動形態を含めて魅力が伝わればいいなと思います。
古川「帯広まで来て頂いて、ありがとうございました!」

地元ファミリー層に人気のおびひろ動物園!
——いやー、私も実際に帯広に行って本当に良かったと思いました。帯広動物園にも行きましたよ!ファミリー感があってすごくいいところでした。
古川「おー!行ったんですか!よかったよかった!」
——ずっと「私は六花亭で働いていて彼氏は帯広動物園の飼育係である」っていう妄想をしていました。帯広で暮らしてもきっと楽しいだろうなって。
古川「絶対楽しいと思いますよ、あの町は。一生暮らせます。帯広だけじゃなくて、そういう町がこれからも沢山見つかったらいいなって思います」
KONCOS
古川太一、佐藤寛によるピアノとギターデュオ。
2012年10月に1stアルバム『ピアノフォルテ』をCD、LP+CDにてリリース。
同年11月より「旅するコンコス~みんなのまちとぼくらのおんがく~」と題し、全国47都道府県48箇所に及ぶツアーを敢行。
今年は3月5日にアルバム『街十色』をリリースし、現在は日本全国100ヶ所をまわるツアーの真っ最中。