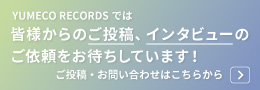近年のFoZZtoneはとても面白い。それは音楽は勿論、バンドの活動もである。ライヴの録音録画可の“REC OK! TOUR”、ライヴのオープニング・アクトに出演する学生バンドの募集、リスナーが選曲し曲順を選んだものがCDになるOMA(Order Made Album)、MV制作の募集などなど挙げればきりがないが、全ての活動が胸をわくわくさせるものだ。その分バンドにとってはとても大変で、骨の折れる作業だろう。音楽に集中できる時間も少ないのではないか……と思ったが、すぐに「ああ、それは違うな」と思った。FoZZtoneにとっては全てが音楽であり音楽活動なのだ。昨年から「2013年は10周年だからいろんな企画をする」とVo/Gtの渡會将士は言っていたが、想像以上にひとつひとつの企画の情報量が多くて、全部をしっかり把握するのがとても大変だった。だがそれが心から嬉しかった。そんなに中身がしっかりあるものをいくつもリスナーに提示して、丁寧に一緒に作ってくれるバンドがいるだろうか。彼らの根本にあるのは「面白いことがしたい」というシンプルなもの。そしてそのシンプルな思いの中には、無限の可能性と野望が広がっている。
前置きが長くなってしまったが、9月7日に開催された『Reach to Mars』ツアー・ファイナルは、胸がいっぱいで苦しくなるほど美しい空間だった。開演前に宇宙飛行士や宇宙船の映像などが流れていたモニターが上がるとカウント・ダウンがスタート。メンバーが1人ずつ順に登場すると渡會が「ようこそ、俺たちの火星、赤坂BLITZへ!」と高らかに叫び、1曲目「世界の始まりに」。鮮やかで痛快なロックンロールが突き抜ける。きっとこの日をメンバー全員が待ち侘びていたのだろう、ステージの高揚が2階席の筆者のもとまでダイレクトに伝わってくる。渡會と竹尾典明のギター隊、菅野信昭と武並“J.J.”俊明のリズム隊でそれぞれ制服風の衣装が合わせられ、なんだか物語に登場するヒーローたちのようだ。エネルギッシュな空気そのままに「茶の花」。渡會は嬉しさの昂ぶりか、言葉のチョイスを間違え曲中で「今日はみんな本当に来てくれてありがとうございました!」とまるでライヴ終盤のようなMC。含み笑いをしつつ「気を付けて帰って下さい! 本当に最高でした!」と続ける彼に、フロアは「おいおい、まだまだ終わらせねーよ!」とツッコミを入れるように更にハイになる。「ワンダーランド」でも、音色が満面の笑みを浮かべるように華やぐ。ステージ上の4人はとても自然体かつ雄大で、全身でこの時間を楽しんでいることがわかる。
荒々しさの中から色気が滲む「ニューオーリンズ殺人事件」、スパニッシュ風味のギターが胸を打つ「情熱は踵に咲く」と畳み掛け、「みんなで力を合わせて、いいライヴにしていきたいと思うわけです」「力の限り楽しんでいこうじゃありませんか!」と叫び「GO WAY GO WAY」「NO WAY NO WAY」へ。竹尾がギターソロ時にステージ中央へ繰り出し、ピンスポットが当てられるという大仰な演出も。本当に隅から隅までメンバー全員が楽しんでいることが伝わり、見ているこちらもどうしたって前のめりになる。「Strike the sun」の後、渡會はこの10年間の音楽シーンの移り変わりについて語り始めた。「FoZZtoneはいついかなるときも聴いてもらえる音楽を作りたい」「老若男女問わず聴ける、いわゆる“王道”ってやつをやろうとずっと思ってやってきたので、死ぬまで(FoZZtoneの音楽を)聴いて下さい」とアコギを構え「BABY CALL ME NOW」。優しく回るミラーボールの明かりと、熱のあるブルースがBLITZを包む。FoZZtoneの音楽は我々に元気を与えてくれる。それは無理やり背中を押すものではなく、「こういう方法もあるけどどうだい?」「こっちにはこんな景色が広がってるよ」と手招きしてくれるような感覚だ。「She said」の後の「Shangri-La」では渡會が前転したり逆立ちしたりとはしゃぐはしゃぐ。広がる景色は南国のような美しさ。ハンドマイクの渡會が片手を振り上げ左右に振ると、フロアもそれを真似してシンガロングとワイパーが起こる。きっと渡會も考える前に体が動いた(手を振り上げた)のだろう。その情景を見て、嬉しさと高揚のあまり笑いが止まらないといった様子だ。渡會が「どんどん新しい何かを探していくのは楽しいね」と語り、11周年への意欲を宣言するとフロアからは拍手と歓声が起こる。ライヴ初披露という初期曲「finch」、「21th Century Rock’n’roll Star」に続いて、アメリカン・ロック・テイストの「GENERATeR」ではフロアのモッシュが高騰。サウンドのグルーヴも更に高まり、ライヴに欠かせない楽曲であることを証明する。
その後渡會がフロアに向かって「いいからお前ら割れろ」とセンターの柵から離れろと命ずる。「いいか、お前ら絶対に俺に怪我をさせるんじゃない(笑)! あと多分、俺、絶対後で怒られる!」と「1983」で、マイク片手に歌いながらその柵の上を歩きフロアの中を歩くというまさかの展開! その画はモーセの十戒の海割れのような、金色の野に降り立つ風の谷のナウシカのような……とにかく奇跡的かつ圧巻である。「すげえ、自分のライヴ見てる!」と笑う渡會はマイクケーブルの限界までフロアの後方へ歩く。「お前ら最高だ、最高のご褒美くれてやる!」と「Master of Tie Breaker」。観客ひとりひとりから力強い〈Yeah!〉〈Master of Tie Breaker!〉という声が上がり、バンドの思いがしっかりフロアに届いていることを実感する。「昔はこんなバンドじゃなかった気がするんだけど……」と笑う渡會は「時間を重ねるごとに“何をやってもいい”という謎の勇気が生まれた」と続けラストに「Reach to Mars」を披露した。その言葉の通り、FoZZtoneの音は清々しい。それは自分たちがやりたいことだけでなく、やるべきこと、やらねばならないことと向き合う覚悟と勇気だ。だから彼らの音はひたすらポジティヴで、大笑いできて、感極まって涙腺が緩むのだろう。
アンコールでは「1回ここに置いていこうかなと思っている曲をまとめてざくっとやりたいと思います」と2006年にリリースされた3rdミニ・アルバム『VERTIGO』収録曲を曲順通りに演奏するというサプライズ。“昔の作品を完全再現する”と銘打ったライヴが多い中、惜しげもなくアンコールで予告なしに行うところもFoZZtoneらしい。今の彼らの音色で蘇る過去曲たちは、新たな色味を帯びて煌めく。中でも「MOB RULE」「水際」では現在の力強さと当時の青い繊細で刹那的が入り混じり、いまがいつの時代なのかわからなくなるような美しい混乱があった。渡會と竹尾がFoZZtoneの前進バンド“ステラ”時代からある「puddle」は2人がアコースティック形態で披露した。ダブル・アンコールで登場した渡會は「もっと面白いことやるから、また遊びに来て」「楽しかった。ありがとう!」と告げる。もはやバンドのアンセムとも言える「LOVE」は、時を重ねるたびにスケールを増す。それはバンドとリスナーが思いを共有するだけでなく、歌う、踊る、手を叩くなどの肉体的な行動でより強固な絆となるのだ。10周年は通過点でしかない。この先の彼らが案内してくれる場所は、いまよりももっと絶景なのだろう。そう信じてやまない。
おき・さやこ●神奈川県横浜市生まれ。2007年に東放学園音響専門学校へ入学。在学中からウェブ媒体などに記事を執筆し、2009年1月に某音専誌編集部のアシスタントとなる。2010年5月からフリーランスライターとして活動を開始。音楽系の媒体やイヴェントサイトなどへの執筆のほか、個人ブログにてインタヴュー企画なども行う。表現で大事にしているのは「本音」と「熱量」。ブログ:http://okkie.jugem.cc/