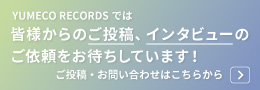1.0
いつの間にか揃えられた視界。
それさえ見えればいいのだと
それだけは見なくてはいけないと
けれども、その澄んだ目は
そんな基準はどこ吹く風で、世界の隅々を見つめていた
見えないことになっているものも、
気付かなくても許されることにも
全部、全部向き合って
誰にも見えてない世界を愛して
嘆いて、泣いて、憤って、笑って、慈しむ
使命感なんてものじゃなくて、たぶん、本能で
そして、その叫びはまた、他者の本能に語りかける
それは壮絶な対話だ
それでも、語りかけることをやめない。
その姿に、愛と敬意を。
この連載を始めるきっかけになったバンドの新しい門出を観てきました。不器用で、過剰で、とても純粋なバンドです。彼等のあたらしい始まりを祝して、今一度このバンドについて書きたいと思います。
■「その眼差しに捧ぐ」 ― The cold tommy新体制を観た

今年2月に、彼らから発表されたニュースは、あまりにも衝撃的だった。ドラム・松原一樹の脱退。昨年7月にメジャーデビューを果たし、ただでさえ桁外れの演奏力が、よりいっそう磨かれてきた、そんな時期だった。だから、寝耳に水だった。
The cold tommyは、研井文陽(Vo/Gt)の感情のどしゃ降りを、音楽と言葉にすることで独自の表現を突き詰めてきたバンドだ。でも近頃は、そのスタンスが変わりつつあった。榊原ありさ(Ba)も積極的に作曲に参加し、メジャーデビューアルバムには研井とのセッションにより生まれた曲も収録されていた。松原もドラマーとしての個性がどんどん色濃くなり、コーラスやMCなどライヴパフォーマンスでも抜群の存在感を示していた。際立った“個”の集合体。3ピースバンドとしての理想形に達してきている、そんな感覚があった。だがしかし、それは長くは続かなかった。それが“何故”なのか、は私が語ることではないから割愛するけれど、とにかく研井、榊原、松原のThe cold tommyは、終わった。
そして4月29日、彼らはホームタウン下北沢で、新ドラマー・マー(ex.folca)を迎えての東京初ライヴを行った。「今日というこの瞬間を、心待ちにして、練り上げてきました。本当に来てくれてありがとう。新しいThe cold tommyです。最後まで楽しんでいってください」。息を呑んでステージを見つめる観客に、まず届けられたのは音楽ではなく、研井の言葉だった。ステージにもフロアにも緊張が走る中、オープニングナンバーは混沌としたヘヴィなロックチューン「バックベアード」。ちょっと、地に足がついていない音がした。続く「パスコード」で感じたのは榊原のベースの変化だった。彼女の作り出すベースラインは、曲の底をねっとりと這いまわるような、重たいグルーヴが特徴。しかし、この日は全く違う聴こえ方をしていた。横のうねりから、縦の弾みへと変わっていたように思う。それは今まで這いつくばっていたものが、スキップを始めてしまうくらいの印象の変化だった。

聴いてゆくうちに、この変化はおそらく彼女の弾くベースが変わったのではなく、ドラムの変化によるものに思えてきた。先程、ベースのグルーヴの話をしたけれど、それはベースに限ったことではなかったのだ。前ドラム・松原の叩くリズムも実は、横に横に連鎖していた。対して、現ドラマー・マーの叩く音は、つま先立ちをしてステップを踏むみたいに、いつも上へ上へと跳ねている。その躍動に、榊原のベースも、トミーの音楽全体も導かれている、そんな風に見えた。
フロア、ステージ双方の緊張感が最高潮に達したのも、それが解けていったのも、「パラドックス」だった。正直、この曲を聴くのが一番怖かったし、楽しみでもあった。私は誰のライヴを観る時も、ものさしにする曲というのがある。ライヴ(ないしはそのツアー)の定番曲の中にも、バンドの調子をはかり易い曲があって、それを基準にその日の状態を観る。それがトミーの場合は「パラドックス」だった。
バンドを代表するダンスナンバーで、私とトミーの出会いの曲。The cold tommyというバンドは常に、目まぐるしく変化をしてきた。ひと月観ないと別物のように演奏や曲のアレンジが変わっていることもしばしば。その中で、バンドと共に変化し、進化してきたのが「パラドックス」だった。
曲に入る直前、「最高のドラマー、マーくんのおかげですごくハッピーです。行こうな、マーくん」、研井が言った。その言葉を受けて、マーのドラムがドン、とこの日一番重たくて熱い音を鳴らした。その後も振り切れたように、ラウドに叩きまくるマー。つられるように、研井のギターもロックに唸る。今まで聴いたどの「パラドックス」よりも、硬質な、いわゆる“ロックンロール”然とした音だった。おそらくこの感じが、今のモードなのだろう。
この日、会場にはマーの門出を祝う仲間たちも多く駆けつけていた。その様子を見た研井が「マーくんと出会ってわかったのは、ハッピーが大事だなってこと。人間が好きで、音楽が好きで、血の通ったものが好きで。それに気付きました。なぜなら、今俺の心がハッピーだから。」と、率直な気持ちを口にした。そしてこのMCの後には新曲も披露された。研井と榊原が、フロアを背にドラムセットに向かい、3人で息を合わせて始める。意外にも、研井のギターがサイレンの様に唸る、初期を思わせる王道のナンバーだった。

メジャーデビューアルバムの収録曲でありアグレッシヴなアンサンブルが特徴の「PLUTO」では、新体制の意地を見せつけた。間奏では個々の演奏スキルと熱をこれでもかとぶつけ合い、白熱したセッションで圧倒する。しかし、殺伐とした空気は一切なく、3人は顔を見合わせる度に、子供のような目をして笑っている。“心がハッピー”なのは研井だけではないのだろう。割れんばかりの手拍子に讃えられながら「ヒステリック」で本編は幕を閉じた。
アンコールの「朝から夜に」を終えると、間髪を入れずに再びアンコールをねだる拍手が鳴り響いた。ダブルアンコールは「リュカの黒髪」。風が吹き抜けていくような流麗なメロディーに乗った研井の歌は、彼の澄んだ目と同じように、淀みなく響き渡った。惜しむらくは、コーラスがなかったこと。全編を通して、課題は山程あるように思う。だけど、同じくらい可能性も見えた。たぶん、今彼らはとても自由で、解き放たれている。喩えるなら、マーチンのブーツに慣れた足が、久しぶりにスニーカーを履いたみたいに。軽くて、嬉しくて、踊るのをやめられない。でも、ふとした瞬間、その軽やかさを心許なく思ったり、がっしりと地に足をつけたくなったりするかもしれない。そうなった時、彼らはどんな靴を選ぶだろうか。今からその瞬間を、楽しみにしている。

■end “ROCK’N” roll vol.4 ― エレファントカシマシ「今宵の月のように」
The cold tommyのライヴで、初めて研井文陽という人物に出会った時、真っ先に思い浮かんだのが、エレファントカシマシの宮本浩次だった。あちこち言葉を散らかしながら喋る姿も、鬼気迫る表情で矢継早に歌うのも、“ミヤジ”みたいだと思った。そして何より、その目に相通ずるものを感じた。透明な目のまま、大人になってしまった人が、ここにも居た、と。濁った目ならば素通りできる物事を全部全部見つめてきてしまった人の、歌う歌。そういうものに、どうやら私は弱いらしい。因みに、The cold tommyにも月を歌う曲がある。〈過剰に揺れる/思い出だけが/僕を許して/月はキレイだ〉(「ヒステリック」)彼らの見る月は、どれ程うつくしいのだろうか。瞼の裏で、想像する。
 イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。守りたいのはロックンロールとロン毛。4月は盛り沢山。先日『音楽と人』デビューを果たしたOutside dandyのレビュー&レポート、前回に引き続きのThe CheseraseraはLOST IN TIMEとのツーマンをレポート前回インタビューしたジャンプザライツのセルフライナーノーツも編集しております。
イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。守りたいのはロックンロールとロン毛。4月は盛り沢山。先日『音楽と人』デビューを果たしたOutside dandyのレビュー&レポート、前回に引き続きのThe CheseraseraはLOST IN TIMEとのツーマンをレポート前回インタビューしたジャンプザライツのセルフライナーノーツも編集しております。