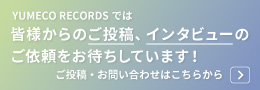東京へ仕事などで新幹線に乗っていますと、「そうだ、京都、行こう」という広告を見ますが、京都という場所は他の地域の方からしますと、憧れに近いものと安心を感じることが多いようで、よくもてなしますと、感激もなされます。京都に着いたときにまず、皆が感動するのは京都タワーでしょうか。東京タワーほどの高さもないものの、その情緒を写真におさめられていきます。また、「空が広い。」と言いますが、それは景観の関係もあり、高層建築物に関して京都は規制がありますので、ビルディングが押し迫ってくる圧迫感がないのかもしれません。ただ、ガイドブックに載っている「京都」はあくまでイメージの京都であり、同時に今は京都でも老舗店も潰れてゆき、チェーン店が増えている現状もあるのも事実です。今回、京都といえば、ということで、くるりというバンドを改めて紹介したいと思います。おそらく、このサイトを見られている方はご存知の方も多いでしょうが、キャリアや音楽的な変遷があり、捉えづらいバンドでもあります。また、アルバムごとに「色」が変わったりもしますので、そこへの影響された音楽も含めて書いていこうと思います。

私にとってのくるりとは、とても身近な存在でありました。最初の出会いは1,000枚プレスという『もしもし』という自主制作アルバムを京都にある新京極通りの「キクヤ」というレコード・ショップで手に入れたことから端を発します。現在もキクヤはあるのですが、ヴァイナルやブートレグ、ブラック系が強い店になっております。手に入れたときは、97年でした。そのときの自分は普通の京都の大学生の一人で、彼らも京都によくあるといいますか、アヴァンギャルドにブルーズとオルタナティヴをソウル・フラワー・ユニオンのようなエッセンスで煮込んだような支離滅裂な若い佇まいがありました。小さいライブ・ハウスで観たとき、既に彼らは酔っ払い気味ながらも、「君を呼ぶ」などの曲を投げ捨てるように演奏をしていたのが懐かしく思い出します。既に、その『もしもし』には現在でも代表曲の一つである「東京」が入っていましたが、チープな電子音とノイズが行き交う前衛的なアレンジメントになっており、センチメントよりも悲痛な岸田氏の咆哮が聴こえるものでした。
くるりの存在は90年代の後半の日本のロック・シーンで決して目立つ存在ではありませんでした。ドラゴン・アッシュやグレイプバインやトライセラトップス、ナンバーガール、スーパーカーといった今でも現役で活動をしているビッグ・ネームもいます。
しかし、その中でも、取り分け、鉄道オタクで眼鏡をかけた岸田氏のインタビューも含め、三人の大学生然としたルックス面からも、立命館大学の“ロック・コミューン”というサークルからの煙草とお酒に埋もれながら、サイケ、ブルーズの沼を抜けてきたのが見えました。
それを受けてのメジャー・デビューのシングル「東京」という“大きなロック”が受け手に印象付けてしまったものの大きさは否めないでしょう。
君がいるかな 君と上手く話せるかな
まぁいいか
でもすごくつらくなるんだろうな
君が素敵だった事 ちょっと思い出してみようかな
(「東京」)
京都から東京に出て、君の「素敵」を思い出すこと。90年代後半で、くるりはふわっとしたモラトリアムの季節を謳歌しているようでもあり、京都に溢れるともいえる、浪人生的な風情のままで、はっぴぃえんどや西部講堂の一時期のうねりを村八分のような捩れではなく、JUDY AND MARYやL’Arc~en~Cielなどでのワークスでも有名な佐久間正英氏のプロデュース・ワークで1999年のメジャー・ファースト・アルバム『さよならストレンジャー』を巧く纏めます。今聴きますと、ウェルメイド過ぎる気がしますが、異邦人にさよならを告げることからデビューをするというのは表徴的であり、その後を思いますと、別離と前進の感情の触れ幅をつねに動く彼らの未来を示唆していたのでしょうか。
さて、サニーデイ・サービス以降のムードと言ってもいいでしょうか、巧く唄うよりも、「朴訥」に歌うスタイルの岸田氏のボーカルがあり、詩情を挟み込んだイメージとしての「京都」があり、そして、京都のあちこちで煮込まれるブルーズ・セッションのカルチャーがありました。
 初めから「老成」の路に居たくるりは、1999年に自らを打破するシフトにアクセルを踏みます。サード・シングル「青い空」での疾走感とサーカズム、金髪になった岸田氏と逆回しPVが印象を残す「街」では、おおよそ、その時期で巷間に溢れていたロック・ソングの規格からは完全に外れていました。「この街は僕のもの」と叫ぶように歌いあげ、京阪電車、見えないミサイル、などの記号群を散りばめ、アート的なもの、オルタナティヴとしての異端で東京的な何か自体に牙を向けることになります。アートと商業性の狭間での葛藤の時期といえるでしょうか。この頃の彼らのインタビュー、特に岸田氏は舌鋒鋭く、現在の小沢健二氏がよく言われます「自意識のイメージ管理」の問題に触れ、明らかに憤怒を示し、どんどん難しいところへ行く覚悟を定めていたようでした。それと加え、90年代後半にシカゴ音響派というものが隆盛し、〈スリル・ジョッキー〉というレーベル界隈のアーティストたち、音そのものの音の遊戯、例えば、トータス、タウン・アンド・カントリーなどを参照にしながらも、ハイ・ラマズ、ステレオラブ辺りの音響構築の巧みさへと意識が向いていることを示していたのも共振していた気がします。
初めから「老成」の路に居たくるりは、1999年に自らを打破するシフトにアクセルを踏みます。サード・シングル「青い空」での疾走感とサーカズム、金髪になった岸田氏と逆回しPVが印象を残す「街」では、おおよそ、その時期で巷間に溢れていたロック・ソングの規格からは完全に外れていました。「この街は僕のもの」と叫ぶように歌いあげ、京阪電車、見えないミサイル、などの記号群を散りばめ、アート的なもの、オルタナティヴとしての異端で東京的な何か自体に牙を向けることになります。アートと商業性の狭間での葛藤の時期といえるでしょうか。この頃の彼らのインタビュー、特に岸田氏は舌鋒鋭く、現在の小沢健二氏がよく言われます「自意識のイメージ管理」の問題に触れ、明らかに憤怒を示し、どんどん難しいところへ行く覚悟を定めていたようでした。それと加え、90年代後半にシカゴ音響派というものが隆盛し、〈スリル・ジョッキー〉というレーベル界隈のアーティストたち、音そのものの音の遊戯、例えば、トータス、タウン・アンド・カントリーなどを参照にしながらも、ハイ・ラマズ、ステレオラブ辺りの音響構築の巧みさへと意識が向いていることを示していたのも共振していた気がします。
当時の私は大学生でしたが、ある種の自意識過剰で、ほぼ大学に通わず、1日を自由に巡ることができる500円の京都市バスのカードを買って、寺社仏閣を巡ったりしていましたが、そんな攻撃的なくるりの雰囲気と自分の若さゆえの不甲斐なさ、やるせなさは合っていた気がします。その頃の私は、京都に関して、大学を通じて、奈良という場所から、外から来た者であるがゆえのしがらみに気付いてきた時期でもありました。
そして2000年になり、リリースされたセカンド・アルバム『図鑑』では、数曲で、ジム・オルークを招聘し、音響への細部への拘りを高めつつ、ささくれた実験要素とある種のパラノイアックなサウンド・センスがポップス、ミニマル、ポスト・ロック、唱歌風などの音楽語彙へ還元され、整合性よりも、「懐の広さ」を一気に顕現させたと言えます。
(*写真は京都の老舗カフェ、喫茶ソワレ)

『図鑑』には、転調が面白い好戦的なギターロック、「マーチ」。00年のミレニアムの狂騒を茶化したアメリカのベックというアーティストの初期を思わせるローファイに編まれた「ミレニアム」。ミニマルに音響の美しさの漣を表象したインストゥルメンタルの「惑星づくり」。拙いピアノに音楽業界システムへの疑義、または、他のメタファーともいえる詩情が乗った繊細な「ピアノガール」。ベースの佐藤氏が作詞・作曲を手掛けた珍しい(基本は岸田氏が作詞・作曲を担います。)「ホームラン」での彼岸性(「ホームランボールは飛んでくるはずはないから フィクションに踊る」といった歌詞が印象深いです。)など多岐に渡った曲が収まっていました。
また、現在の彼らの中でも重要曲の「宿はなし」では、リズムのボトムを落とした日本伝承の唱歌の温度を取り入れ、天邪鬼バンドの本懐をようやく見せた作品として、その舵取りに一気にロック・リスナーの注視が集まることになりました。その『図鑑』の尖りから、今度はポスト・ロックへ片足を置いたまま、大胆な打ち込み、ダンス方面に踏み込みます。エンジニアの高山徹氏のミックスした2000年の「ワンダーフォーゲル」は今も人気曲ですが、ロックとダンスの昂揚感にバンドとしてこれからどのように進むかにあたっての葛藤を詰め込んだ切ない疾走を含みこんだシングルで、遂に老成から青春へ回巡します。その後、ダフト・パンク、アンダーワールド、ケミカル・ブラザーズ辺りのロックとダンスを折衷させたアクトのサウンドを取り入れた形で、キャリア上でも屈指のシーケンスが巡る果敢無くも青春の終わり、ジンジャエールの味と、最終バスを乗り過ごす接点を「君への距離感」で柔らかくつないだシングル「ばらの花」が2001年初頭にリリースされます。その上がりも下がりもしない曖昧を往来するメロディーと、印象的なギターリフ、そして、ポエトリーとしても美しい歌詞が重なったその曲は、その後、矢野顕子さん、小田和正さん、奥田民生さんなど錚々たるメンバーからの称賛を受けることになります。
 この頃はメロディー・メイカーとしての岸田氏の評価軸も定められ、くるりというバンドの真価、牙が見えてきた季節ともいえます。バンド史の前後を分かつ、ハイファイ且つ大胆なダンス・エレメントを入れた「永遠」、「C’mon C’mon」などが入りながらも、「カレーの歌」や「リバー」といった叙情も混ざった2001年の『TEAM ROCK』は当時のユースたちを明らかに鼓舞せしめましたが、そのツアー中、大阪のIMPホールという場所で私は観たのですが、かなり人が詰まっていながらも、いささかとっ散らかったファン層、年代の人たちが居ました。なお、このライヴでは、DJタイムがあったり、オーディエンスにダンスを求めるなど、この時代におけるロックとダンスの壁や、さらにはメンバー間の軋轢など辛いものもあったようでした。今や、サカナクションやザ・テレフォンズが当たり前にやっていることがその当時では難しかったと言えるかもしれません。DJタイムで、抜けていくロック・ファンを観ながら、私は彼らの来し方と今後を思いました。
この頃はメロディー・メイカーとしての岸田氏の評価軸も定められ、くるりというバンドの真価、牙が見えてきた季節ともいえます。バンド史の前後を分かつ、ハイファイ且つ大胆なダンス・エレメントを入れた「永遠」、「C’mon C’mon」などが入りながらも、「カレーの歌」や「リバー」といった叙情も混ざった2001年の『TEAM ROCK』は当時のユースたちを明らかに鼓舞せしめましたが、そのツアー中、大阪のIMPホールという場所で私は観たのですが、かなり人が詰まっていながらも、いささかとっ散らかったファン層、年代の人たちが居ました。なお、このライヴでは、DJタイムがあったり、オーディエンスにダンスを求めるなど、この時代におけるロックとダンスの壁や、さらにはメンバー間の軋轢など辛いものもあったようでした。今や、サカナクションやザ・テレフォンズが当たり前にやっていることがその当時では難しかったと言えるかもしれません。DJタイムで、抜けていくロック・ファンを観ながら、私は彼らの来し方と今後を思いました。
2001年秋からの初の海外、ロンドン郊外でのレコーディングに入り、シングル候補が見当たらないという状況下で、ふとドロップされたのが今でも日本におけるフロアー、ロック、オルタナティヴの垣根を越えた「ワールズエンド・スーパーノヴァ」になります。安藤裕子さんも最近ではカバーされておられましたが、柔らかな打ち込みに、「絶望の果てに希望を見つけたろう 同じ望みならここでかなえよう ぼくはここにいる 心は消さない」という優しさと毅然たる姿勢の歌詞が染みる佳曲です。ただ、この頃、後に、正式メンバーになる大学時のサークルの先輩のギターの大村達身氏を招き入れ、岸田繁氏、佐藤征史氏、森信行氏という当初からのフォーメーションに新色が加わります。ここから、くるりは「バンプ・オブ・チキン的な運命共同体的なバンドに憧れる。」という岸田氏の言があったように、メンバーの入れ替わりなどが激しくなり、転げてゆく道を進みます。

「ワールズエンド・スーパーノヴァ」を筆頭に、民族、辺境の音楽や音響美、ロック、ダンス、などこれまでのくるりの全要素を横断的に、多文化次元主義的に総括してみせた、タイトルそのものの2002年の『THE WORLD IS MINE』は茫漠とした淡さとスクエアな音空間がぼんやりとした透度を孕む「過渡期」を示唆する作品でした。「水中モーター」での幼児退行感と「男の子と女の子」の完全なる老人の視点が混ざり合いながら、ネオテニー的な可塑性で振れる作品と捉えてもいいでしょう。
僕達はみんなだんだん歳をとる
死にたくないな と考えたりする
(「男の子と女の子」)
諦観と幼き欲動が混ざり合っての、世界は私のもの――。それは、ゼロ年代の始まりの終わりの物悲しさにダイレクトにプラグ・インして、真ん中のレフトサイドからのボールを投げつつも、オルタナティヴに音楽を鳴らそうとする、くるりの混迷を示していた気もします。
03年はゆえに、必然的とも言える暫しの沈黙が入ります。また初期メンバーの森氏の脱退や自らのスタジオ・ペンタトニックの設立、様様な難解な事柄を孕んだ時期の中での、「How To Go」でのリ・スタート。UKのビージーズの「How Deep Is Your Love」へのオマージュを含んだメロディーに重厚なギターがどっしりと響く6分を越えるシングル向けとはいえない曲でのシーンへ復帰しました。「昨日の今日からは一味二味も違うんだぜ」(「HOW TO GO」)と、これまでのくるり自体にくるりが線を引きながらも、「毎日は過ぎてく でも 僕は君の味方だよ」(同曲)と表明。以前からライヴでは演奏されていましたが、正式録音でおさめられた「すけべな女の子」、大人になるな、というフレーズが残る「地下鉄」と粒揃いの曲群が集まったこのシングルで、新しいくるりは再始動します。
ピンク・フロイド、イエス、ザ・バンドのようなプログレッシヴ・ロック、オールド・ロックへの傾斜、ジャム・セッションを主体としたアナログで泥臭いモードに入ってゆく過程で、何らかの文脈で青春世代の犠牲者的な部分もあった彼らは「割礼」として、クリストファー・マグワイアをドラマーとして正式加入させて、大人向けのロックンロールへと一気に進み、2004年の『アンテナ』というライヴでこそ映える男気溢れるアルバムをベースに全国をバンドワゴンで巡り、各地で、重厚なパフォーマンスをしてみせていました。この頃の、男気溢れるくるりのフォーマットでのライヴ・パフォーマンスを愛する人たちもいまだに多いですし、私もライヴを何度か観ましたが、骨太で非常に心地良いジャム・セッション、インプロビゼーションの部分に真価を見出せるものだったのは確かでした。初のワンマンでの武道館公演も行ないながらも、クリストファーありきのアルバムだったというのもあり、必然的にと言いましょうか、クリストファーはこのアルバム、ツアーをもって脱退します。
この時に、私はくるりは随分、思えば遠く来たなと思いましたが、結局は彼らの地下水脈に流れる叙情が失われていないのを感じ、フォーマットの変化により、もはや、初期のくるりが想い出せないほどのくるりになっていても、そこでひねくれ方にまだ、私は信頼していこうと思っていたのでした。長いジャム・セッションで退屈そうに欠伸をした当時の恋人を横目に。冒険を進めてゆく彼らに個人的に胸は打たれたまま、で、そこにはもう”京都”も”ブルーズ”も”サイケ”もなく、一ロック・バンドとしての凛とした佇まいを感応しました。
 クリストファーの脱退後、岸田氏と佐藤氏はCoccoとのプロジェクト・バンドのSINGER SONGERを始めるなど、フットワークの軽さを見せつつ、2005年のシングル「The Birthday」は、岸田氏が自らの加齢化に自覚的になってきたからこそ、生まれたという詩情溢れる爽快なギターポップになっています。翌年の2006年からの「Superstar」でのパワーポップ、京浜急行電鉄の依頼によって成り立った「赤い電車」のエレ・ポップ、「Baby I Love You」で見えた柔らかなレイドバックは、その都度の嗜好、嗅覚でサウンド・スタイルを変えてゆくUKのプライマル・スクリーム的なものも感じながらも、これまでのねじれとアヴァンギャルド性を敢えて封印して、プリミティヴな発想に焦点を絞り、古のブリティッシュ・ロックやモッズの影響を3分間ポップのマジックの中に閉じ込めた2005年の『NIKKI』というアルバムに結実することになります。初期のビートルズ、ザ・フー、スモール・フェイセスなどマージービートを経由して、英国音楽への歴史を測ることで、呼吸を確認するような、軽快な内容になっていました。
クリストファーの脱退後、岸田氏と佐藤氏はCoccoとのプロジェクト・バンドのSINGER SONGERを始めるなど、フットワークの軽さを見せつつ、2005年のシングル「The Birthday」は、岸田氏が自らの加齢化に自覚的になってきたからこそ、生まれたという詩情溢れる爽快なギターポップになっています。翌年の2006年からの「Superstar」でのパワーポップ、京浜急行電鉄の依頼によって成り立った「赤い電車」のエレ・ポップ、「Baby I Love You」で見えた柔らかなレイドバックは、その都度の嗜好、嗅覚でサウンド・スタイルを変えてゆくUKのプライマル・スクリーム的なものも感じながらも、これまでのねじれとアヴァンギャルド性を敢えて封印して、プリミティヴな発想に焦点を絞り、古のブリティッシュ・ロックやモッズの影響を3分間ポップのマジックの中に閉じ込めた2005年の『NIKKI』というアルバムに結実することになります。初期のビートルズ、ザ・フー、スモール・フェイセスなどマージービートを経由して、英国音楽への歴史を測ることで、呼吸を確認するような、軽快な内容になっていました。

そこからはリップ・スライムとのコラボレーション、自らのキャリアの主要曲をコンパイルしたベスト・アルバムがセールス的な成功します。ちなみに、このベスト・アルバムのブックレットでは京都の色んな場所が写真としておさめられています。しかし、大村氏は2007年2月に正式脱退し(くるりは、岸田氏と佐藤氏のバンドだと思ったと言っていました)、ついには二人となってしまい、ウィーンへ訪れたのもあり、クラシックにのめり込みながら、過酷なウィーンでのレコーディング作業に入ることになります。ミックスやマスタリングの関係もあり、フランスのパリ、ロンドン、日本と音楽への殉教精神にも近い何かは鬼気迫るものがあり、それは「言葉はさんかく こころは四角」での初回盤に付属していましたDVDのドキュメンタリーを観たら、分かります。大胆にストリングスを取り入れながらも、これまで通り静謐なバラッド「レンヴェーグ・ワルツ」、前衛的なロック「アナーキー・イン・ザ・ムジーク」、アイリッシュ・トラッド的な「スロウダンス」、ジプシー・ミュージック調の「ハヴェルカ」など多彩な曲が並ぶ2007年の『ワルツを踊れ』は多くの方々に高い評価も得ました。
こうして考えてみますと、くるりとは岸田氏の気紛れで成立しているバンドなのか、という方もいるかもしれません。残念ながら、昨年で終わりになってしまいましたが、学生が主体になって京都で行なう“みやこ音楽祭”というイベントの2008年での“きしだしげる”名義でのステージでは、焼酎を飲みながら、サラッと「ランチ」や「街」などを歌っていましたが、岸田氏の背景に広がるスクリーンがくるりであり、そこには初期から共にする佐藤氏の存在も大きいのでしょうし、くるりとして主催している京都音楽博覧会で過去メンバーの森氏や大村氏を呼び、セッションする姿勢からして、もはや、くるりとは「屋号」ともいえるとしたら、『ワルツを踊れ』からの進み方は荊も含んでいた部分があります。
 54-71のボボ氏をドラマーに入れて、世武裕子さんのピアノを援用した上での、アーヴァンかつ、ダウン・トゥ・アースな質感を持ちながら、過去にないくらいの剥き出しになったアルバム『魂のゆくえ』では以前の自身の曲「ハイウェイ」での「身ぐるみはがされちゃいな」というリフレインが聞こえる内容にもなっていました。あまりに「素」の雰囲気で、意匠も作為性も何もないシンプルなものであり、常に、ある意味でミーハーに都度の音楽スタイルに配慮をして、カウンター的に問題提起をしてきた彼らが、純然と京都から東京へ出てきたくるりのハードな来し方を踏まえて作った裸一貫の『魂のゆくえ』。そこで、「つらいことばかり」と歌うのも分からないでもない痛みも見える内容になっていた気がします。
54-71のボボ氏をドラマーに入れて、世武裕子さんのピアノを援用した上での、アーヴァンかつ、ダウン・トゥ・アースな質感を持ちながら、過去にないくらいの剥き出しになったアルバム『魂のゆくえ』では以前の自身の曲「ハイウェイ」での「身ぐるみはがされちゃいな」というリフレインが聞こえる内容にもなっていました。あまりに「素」の雰囲気で、意匠も作為性も何もないシンプルなものであり、常に、ある意味でミーハーに都度の音楽スタイルに配慮をして、カウンター的に問題提起をしてきた彼らが、純然と京都から東京へ出てきたくるりのハードな来し方を踏まえて作った裸一貫の『魂のゆくえ』。そこで、「つらいことばかり」と歌うのも分からないでもない痛みも見える内容になっていた気がします。
 『魂のゆくえ』から、B面集『僕の住んでいた街』、『言葉にならない、笑顔を見せてくれよ』、『ベスト・オブ・くるり2』と、弛緩とシンプルなバンド・サウンドではっぴぃえんどからニルヴァーナ、ローリング・ストーンズ、カントリー的なものを跨ぎながら、昨年の『ベスト・オブ・くるり2』が象徴していたように、明らかに、くるりはもうオルタナティヴのサウンドを目指すのではなく、一生活者のほんのささやかな吐息を支える側に立ったと言ってもいいのでしょう。五人体制になって(すぐにドラマーが抜けましたが。)、京都へ拠点を移した現在のくるりは、初のチャリティー・シングルとしてリリースする「石巻復興節」といい、使命感を背負いながらも、世を想う在り方になってきてもいます。
『魂のゆくえ』から、B面集『僕の住んでいた街』、『言葉にならない、笑顔を見せてくれよ』、『ベスト・オブ・くるり2』と、弛緩とシンプルなバンド・サウンドではっぴぃえんどからニルヴァーナ、ローリング・ストーンズ、カントリー的なものを跨ぎながら、昨年の『ベスト・オブ・くるり2』が象徴していたように、明らかに、くるりはもうオルタナティヴのサウンドを目指すのではなく、一生活者のほんのささやかな吐息を支える側に立ったと言ってもいいのでしょう。五人体制になって(すぐにドラマーが抜けましたが。)、京都へ拠点を移した現在のくるりは、初のチャリティー・シングルとしてリリースする「石巻復興節」といい、使命感を背負いながらも、世を想う在り方になってきてもいます。
同一延長線上に似たような作品がないといえども、組織体としても常々変容し、それをして、支離滅裂だとか、気紛れが過ぎるだと言う向きもあるでしょう。それでも、くるりは解散もせずに、京都の中でもある様々な柵を掻き分けながら、ベースの京都から音楽を今、紡ごうとしています。成熟から若返りのメビウス輪のような感情を行間から滲ませて。もう別離の切なさやハローもグッバイもサンキューも言えなくなること、ではなく、「明日」を唄っていくならば、くるりは、こういう悲しみと非情な摂理が表れてきた世に向けて、フィクションかもしれなくても、京都的な風合を運んでゆくのではないか、そんな気もします。
「京都的な風合」とは、私はおそらく柔らかさと厳しさの共存だと感じます。
ソトものが観光に来ると、これだけ厚くもてなす場所はないでしょう。ただ、ウチに居ますと、伝統と歴史に息が詰まりそうになるほどの予めのルールと規律だらけです。くるりの運んだ京都的な風合は京都に一端、居を構えた人なら分かり得るでしょう、イメージとしての京都です。京都という場所の深みと、くるりが京都をある種、代表しているバンドというのは、それもフィルターがかかっています。ただし、京都には広い空が、多くの学生が、独自のオルタナティヴな文化が根付いています。そういう意味で、私は京都への親近的な愛憎があり、それがずっと追いかけてきたくるりにもあります。ばらの花が散っても、虹が架からなくても、「いつまでも そのままで泣いたり笑ったりできるように」(「奇跡」)といえる義務が今、彼らにはあるなら、まだ私は彼らを信じたいと思っております。
非常に僭越ながら、この文章を読んだ方々が何らかの契機となって、京都やくるり、更にはくるりの背景にある音楽について触れてみたりすることになれば、これ以上の幸せはありません。
バスが来た
見知らぬ行き先に微笑む
君の横顔がまぶしくて
海へ行こう
そしてまた名前を呼ぶよ
ここは名もなきバス停だよ
ここは旅のまだ途中だよ
(「旅の途中」)

まつうら・さとる●1979年生まれ、大阪府出身。好きなアーティストはレディオヘッド、ブラー、スピッツ、小沢健二、くるり。最近で興味があるバンドは赤い公園や0.8秒と衝撃です。現在は、東アジア経済圏域の研究員をしながら、音楽メディアCOOKIE SCENEなどを主体に多岐に渡る執筆活動も行なっています。大学を出て、一度、普通に働き、大学院にまた入り、人の繋がりの中でこうして今の場所にいます。音楽が好きになったのはどんな国へ行っても、言語を越えられる意味も含めて、おそらく、原体験は5歳の頃にドイツに居たときにラジオで聴いたドリス・デイかもしれません。しぶとくも真摯に30代を過ごしていきたいと思っております。
。