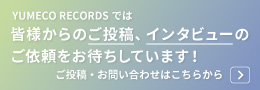某月某日:今日もまた暗闇の中へ。Bunkamura ル・シネマで、『危険なプロット』を鑑賞。フランス映画です。“フランス映画”という言葉が、今、どんなイメージで響くのか定かではありませんが、“ヌーヴェル・ヴァーグ”なんてものは、今や昔。とはいえ、『最強のふたり』や『タイピスト!』、最近では『ムード・インディゴ』など、意外と観る機会が無いわけでもないフランス映画。しかし、ほぼ毎年のように新作を撮り続け、しかもそれがすべて日本で公開され続けているフランス人監督って、今やひとりしか思い浮かびません。それは誰か? フランソワ・オゾンです。
某月某日:今日もまた暗闇の中へ。Bunkamura ル・シネマで、『危険なプロット』を鑑賞。フランス映画です。“フランス映画”という言葉が、今、どんなイメージで響くのか定かではありませんが、“ヌーヴェル・ヴァーグ”なんてものは、今や昔。とはいえ、『最強のふたり』や『タイピスト!』、最近では『ムード・インディゴ』など、意外と観る機会が無いわけでもないフランス映画。しかし、ほぼ毎年のように新作を撮り続け、しかもそれがすべて日本で公開され続けているフランス人監督って、今やひとりしか思い浮かびません。それは誰か? フランソワ・オゾンです。
そんなオゾンの最新作である『危険なプロット』。一瞬、フロイトとユングの師弟関係を描いたクローネンバーグの映画『危険なメソッド』と見間違えてしまうような邦題――というか、『危険な情事』あたりから延々と続く、この“危険な~”シリーズとは、いったい何なのでしょう? といった疑問が湧かないでもないですが、原題は“DANS LA MAISON”――英題はそのまま“IN THE HOUSE”ということで、まさしく“家の中で”といった趣向の映画になっているようで。
 物語は比較的単純です。作家になる夢をあきらめ、高校生相手に作文の指導をしている国語教師(ジェルマン/ファブリス・ルキーニ)は、ひとりの生徒(クロード/エルンスト・ウンハウワー)が提出した“作文”に非凡なものを感じ、個別指導を開始します。文章の書き方から“プロット”の構成法まで。それを受けて、“作文”の続きを書き進めてゆくクロード。しかし、問題は彼が提出し続ける“作文”の内容です。そこには、彼があるクラスメイトの家を訪れ、その鋭い観察力で描写した“ある家族”の生々しい姿が綴られているのです。どこまでが本当で、どこからが嘘なのか。次第にインモラルな領域へと突入してゆくクロードの“作文”。そこにある種の危うさを覚えながらも、物語の続きが気になってしょうがないジェルマン。やがて、クロードの“作文”は、その読者であるジェルマン自身の夫婦関係をも描き始めてゆき……。
物語は比較的単純です。作家になる夢をあきらめ、高校生相手に作文の指導をしている国語教師(ジェルマン/ファブリス・ルキーニ)は、ひとりの生徒(クロード/エルンスト・ウンハウワー)が提出した“作文”に非凡なものを感じ、個別指導を開始します。文章の書き方から“プロット”の構成法まで。それを受けて、“作文”の続きを書き進めてゆくクロード。しかし、問題は彼が提出し続ける“作文”の内容です。そこには、彼があるクラスメイトの家を訪れ、その鋭い観察力で描写した“ある家族”の生々しい姿が綴られているのです。どこまでが本当で、どこからが嘘なのか。次第にインモラルな領域へと突入してゆくクロードの“作文”。そこにある種の危うさを覚えながらも、物語の続きが気になってしょうがないジェルマン。やがて、クロードの“作文”は、その読者であるジェルマン自身の夫婦関係をも描き始めてゆき……。
他者の侵入によって、次第に狂い始めてゆく“家族”――というテーマから想起されるのは、オゾンの初期作品『ホームドラマ』です。そして、ある事件によって“家族”の秘密が次々と明らかになってゆく――という展開から想起されるのは、オゾンの代表作『8人の女たち』です。原作はスペインの戯曲とのことですが、オゾンがこの物語のなかに、自らが撮り上げて来た映画と共通するものを感じたのは、ほぼ間違いないでしょう。実際、彼はこんなふうに語っています。「この戯曲を通して、私自身がどういうふうに映画を撮っているのか、どういうふうにストーリーや人物を語っていくのか、また創造するとはどう いうことか、私の映画作りの方法を語ることができるのではないかと思ったのです」。
いうことか、私の映画作りの方法を語ることができるのではないかと思ったのです」。
しかし、この映画で特筆すべきは、やはり主人公クロードを演じるエルンスト・ウンハウワーの非凡な存在感でしょう。オゾンと言えば、女優を美しく撮ることで知られていますが、ゲイであることを公言している彼の審美眼がいかんなく発揮されるのは、やはり男優のセレクト。個人的には、いちばん好きなオゾン作品である『ぼくを葬る』のメルヴィル・プポーしかり、ただのイケメンではなく、どこか暗さや危うさを秘めた艶やかな男たち。しかも今回は、老インテリをはじめ、男女問わず惹きつけてやまない、魔性の“美少年”という役どころです。薄い笑みを湛えたメイン・ビジュアルの印象そのままに、この難しい役どころをほぼ完璧に演じてしまっているエルンスト君。正直、ヤバいです(汗)。
さらに、これは後から知って、非常に驚いたのですが――映画は、ジェルマンが務める高校(つまりクロードが通う高校)が、来季から制服を採用することを決定するという、ちょっと不思議なシーンからスタートします。というのも、実はフランスのリセ(日本の高校にあたる)に、制服は存在しないから。ブレザーとネクタイ。別によくわかってないのに、「ああ、オゾン、わかってるね!」と思わず膝を打ってしまいそうになりましたが、そう、そもそもの始まりからして、オゾンの妄想の産物なのです。制服をラフに着こなした美少年……うほっ! 冗談です。
オゾンの妄想力は、別の場所にも発揮されています。劇中、ジェルマン夫妻が映画『マッチポイント』を観にゆくという非常にわかりやすいシーンがありますが、昨今のオゾンは、どうやらウディ・アレンを大いに意識しているようなのです(確かに、オゾンの前作『しあわせの雨傘』は、ほとんどウディ・アレン映画のようでした)。実際問題、本作におけるジェルマン夫妻は、ウディ・アレンとダイアン・キートンをイメージしているとのことだし、いわゆるウディ・アレン的な“狂言回し”として、ジェルマンは終盤、リアリズムの枠をやすやすと超えて、大活躍し始めるのです。そう、ジェルマンを撹乱させていった“危険なプロット”は、やがて観ている我々自身をも撹乱させてゆくのです。
そして、最後に迎える衝撃の結末。どうやらオゾンは、そのラスト・ショットのイメージから、逆算的に物語を構築していったようなのです。詳しくは書きませんが、他者の生活をのぞき見たいという好奇心によって繋がれた、緩やかな共犯関係。そのイメージはあまりにも雄弁で、僕のなかにいくつかのものを連想させるのでした。アンドレアス・グルスキーの写真、ザ・ストリーツのアルバム、そしてフランスが誇る俳優・映画監督ジャック・タチの『プレイタイム』。かくもおかしき我々の生活。
そう、ひとつ言い忘れましたが、『危険なプロット』は、スリリングなサスペンスである以上に、とても皮肉の利いた(“エスプリ”って言うの?)コメディなのだと僕は思います。『8人の女たち』が、そうであったように。特に、人の良さと頭の弱さから、クロード君に目をつけられたクラスメイト、ラファ君の顔面が打ち放つ圧倒的な説得力と、「バスケしようぜ!」とか言いながら部屋に入って来るラファ君のパパ(なぜか中国かぶれ)、そしてジェルマン夫人が勤務するギャラリーに展示してある“現代美術”の度肝を抜くような趣味の悪さは、ホントに爆笑ものでした。しかし、決して笑いっぱなしで終わらせないのが、オゾンがオゾンたる理由だったりもして……。観終えたあとの、このなんとも言えない感覚は、是非スクリーンで体験していただきたいと思います。
 ついでに。映画のエンドロールが終わったあと、突如スクリーンに映し出されたものがありました。それは、オゾンの次回作“JEUNE & JOLIE”(英題“YOUNG & BEAUTIFUL”)が、『17歳』という邦題のもと、来年2月に公開されることが決定したというニュースでした。主演は、コケティッシュな魅力が鮮烈な、気鋭の新進女優マリーヌ・ヴァクトです。ええと……美少年もいいんですけど、やっぱ美少女が見たいです(ちなみに、『危険なプロット』には若い娘がひとりも出て来ないので要注意)。しかも、邦題が『17歳』とは(前回のコラム参照)! オゾンが描く17歳の性! ということで、ある筋ではオゾンの最高傑作との呼び声高い『危険なプロット』ですが、ワタクシの興味は、早くも次回作のほうへと移っているのでありました。マイアヒ。
ついでに。映画のエンドロールが終わったあと、突如スクリーンに映し出されたものがありました。それは、オゾンの次回作“JEUNE & JOLIE”(英題“YOUNG & BEAUTIFUL”)が、『17歳』という邦題のもと、来年2月に公開されることが決定したというニュースでした。主演は、コケティッシュな魅力が鮮烈な、気鋭の新進女優マリーヌ・ヴァクトです。ええと……美少年もいいんですけど、やっぱ美少女が見たいです(ちなみに、『危険なプロット』には若い娘がひとりも出て来ないので要注意)。しかも、邦題が『17歳』とは(前回のコラム参照)! オゾンが描く17歳の性! ということで、ある筋ではオゾンの最高傑作との呼び声高い『危険なプロット』ですが、ワタクシの興味は、早くも次回作のほうへと移っているのでありました。マイアヒ。
むぎくら・まさき●LIGHTER/WRITER インタビューとかする人。音楽、映画、文学、その他。基本フットボールの奴隷。