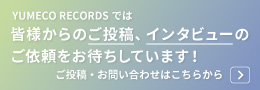某月某日:今日もまた暗闇の中へ。日比谷TOHOシネマズ シャンテで『トゥ・ザ・ワンダー』。最初に断っておくけれど、2011年に観た映画の中で“ベストワン”は、誰が何と言おうとテレンス・マリックの『ツリー・オブ・ライフ』だから。ロードショー中に珍しく2回劇場に観に行ったしな。個人的には、それぐらい強いインパクトがありました。そういう人間による文章だということを、心のどこかに留めておいてください。そして、そのテレンス・マリック監督の新作――それが、この『トゥ・ザ・ワンダー』という次第です。まずは、予告編をご覧あれ。
あー、これ、どう考えても、傑作の予感しかしないわー。まあ、なんと美しいフィルムなのでしょう。ということで、公開早々、割と鼻息荒めで劇場に馳せ参じたわけですよ。「新生児のように、私は目を開く。そして溶ける、永遠の闇に。光を放ち、炎の中へと落ちていく」――そんなモノローグから、流れゆく車窓の風景へ。荒いデジタルの画像で切り取られたフレームの中で、さほど若かくはない男女が無邪気にはしゃいでいます。そして、列車は間もなく、パリ、モンパルナスに到着する……。
物語は、概ね予告編の通りです。アメリカ人男性、ニール(ベン・アフレック)が、パリでウクライナ人女性、マリーナ(オルガ・キュリレンコ)と恋に落ち、オープンカーを駆って、“世界遺産”モンサンミッシェルを訪れる――までが、最初の10分といったところでしょうか。あらかじめ言っておきますけど、モンサンミッシェルは、以降ほとんど出て来ません。映画の主な舞台は、その後ふたりが移住するアメリカ、オクラホマの田舎町でございます。
先程、物語は概ね予告編通りと書いたけれど、通常の映画のようにストーリーが“物語られる”ことはありません。そう、この映画、ほとんど台詞が無いのです。あったとしても、大概は意味深長なモノローグ(「私たちは階段を上った、“感動”を求めて」とか)で、通常の会話(ダイアローグ)は、もはやほとんど消え去ってしまいました。で、その代わりと言ってはアレですが、今回もまた、度肝を抜くような美しさと完璧な構図で切り取られた風景が、ムチャクチャ雄弁に語りかけるのです。あまりにも雄弁過ぎて、もはや意味など拡散してしまうほどに……。
『トゥ・ザ・ワンダー』は、前作『ツリー・オブ・ライフ』と同じく、“マリック・システム”とでも言うべき手法で撮られた映画です。説明します。“マリック・システム”に脚本は存在しません。しかし、個々の役柄については綿密な設定が与えられており、役者は共同生活の中で四六時中その役であることを求められます。それを、名匠エマニュエル・ルベツキが、徹底的に撮影する。とにかく撮影するのです。いわゆる“マジック・アワー”と呼ばれる日の出間際&日没直後のシーンをふんだんに盛り込みながら、そうでないときは役者が太陽を背負う形(つまり“逆光”)で撮影する。基本的にすべて自然光で撮影し、照明どころかレフ板ひとつ用いないのだとか。参考までに、同様の手法で撮られた前作『ツリー・オブ・ライフ』の予告編をご覧ください。
ああ、ほとんど同じですね(若干、“謎”のシーンが差し込まれていますが……)。そして、官能的なまでに美しい。話を戻します。実際問題『トゥ・ザ・ワンダー』は、『ツリー・オブ・ライフ』以上に美しいシーンが立て続けに押し寄せて来るような、「嗚呼、“眼福”とはこのことか!」ってくらい美麗な映画でした。特に、フレームの中でクルクルと表情を変えながら舞い踊るオルガ・キュリレンコのキュートなこと! ニールの幼馴染みの女性、ジェーンを演じるレイチェル・マクアダムスも、非常に美しく撮られていました(バイソンに囲まれたシーンの美しさと言ったら!)。
 でもね……結論から言うと、何かピンと来なかったんですわ、この映画。で、何でだろ? と思いながらネットをいじくっていて、ある心無い感想が目に留まりました。「“金麦”のCMが2時間続く映画(笑)」。マジか! 巨匠マリックの映画を“金麦”扱いとは! 一部おっさん連中はともかく、女性たちから滅法評判の悪い“金麦”のテレビCM。檀れいがはっちゃけているアレですよ、アレ。恐らく、男性目線と思われるフレームの中で、自由奔放に愛嬌を振りまきながらクルクルと舞い踊るオルガ・キュリレンコの一連のシーンを、“金麦”的と称しているのでしょうが、あのCMの“気持ち悪さ”の主な原因は、「相手の男性の存在感が希薄」という点にあってだな、それと比べると俺たちのベン・アフレックは……ん?
でもね……結論から言うと、何かピンと来なかったんですわ、この映画。で、何でだろ? と思いながらネットをいじくっていて、ある心無い感想が目に留まりました。「“金麦”のCMが2時間続く映画(笑)」。マジか! 巨匠マリックの映画を“金麦”扱いとは! 一部おっさん連中はともかく、女性たちから滅法評判の悪い“金麦”のテレビCM。檀れいがはっちゃけているアレですよ、アレ。恐らく、男性目線と思われるフレームの中で、自由奔放に愛嬌を振りまきながらクルクルと舞い踊るオルガ・キュリレンコの一連のシーンを、“金麦”的と称しているのでしょうが、あのCMの“気持ち悪さ”の主な原因は、「相手の男性の存在感が希薄」という点にあってだな、それと比べると俺たちのベン・アフレックは……ん?
ベン・アフレックの存在感? そう言えば、冒頭から何となく見切れがちというか、ちゃんと画面に収まってなかったような……。ブラッド・ピットは、たとえ五分刈りのおっさんスタイルであろうとも、あんなに神々しくアップで撮ってもらっていたのに……。ってか、ベン、ほとんどしゃべらなかったよな? そもそも“ニール”っていう役名知ったの、エンドクレジットだったし(汗)。そう、彼は何を考えているのかサッパリわからない“巨大な空洞”として、映画の中心にいるのです。
もちろん、それはベン・アフレックのせいではありません。近作に限って言えば、実は自らの体験をもとにした“私小説”的な映画ばかりを撮っているマリック。『ツリー・オブ・ライフ』で描かれる“家族”が、彼自身の記憶の中にある“家族”だったように、(ブラッド・ピットの役が、マリックの父にあたります)、『トゥ・ザ・ワンダー』もまた、彼の実体験をもとにしているようなのです(マリックは80年代、パリで隠遁生活を送っていた際、あるシングル・マザーと恋に落ちたとか)。つまりは、ベン・アフレック演じるニールこそ、マリック自身なのです。
一切の取材を受けないどころか、表舞台に顔を出すことすら皆無であるがゆえに、“生きる伝説”と称されているテレンス・マリック。しかし、どうやら彼は、自らが“見たもの”を美麗かつ叙情的に描くことに長けている一方、自分自身を“語る”ことに、ある種のためらいを持っているように思えるのです。『ツリー・オブ・ライフ』にも、マリックの化身たる役柄(成長したブラピの息子役)としてショーン・ペンが登場しますが、これがほとんど何も語らない、演じているショーン・ペン自身、どんな役だかわからなかったという恐るべき人物に仕上がっていました。でも、『ツリー・オブ・ライフ』にとって、それはさほど問題ではありません。映画の中心にいるのは、ブラッド・ピットとジェスカ・チャスティンが演じる夫婦だから。たとえ、その“まなざし”の主体が、少年時代のマリックだったとしても。
しかし、『トゥ・ザ・ワンダー』は、そうではありません。ただでさえ通常のやり方で物語を描かないマリック映画にあって、その中心にいる人物が“巨大な空洞”とは……。どんなに女優が美しかろうと、どんなに景色が美しかろうと、これでは残念ながら映画に入って行くことができないのです。美しいものは、ただ美しいものとしてそこにあるだけで、観る者の心の深いところに入って来ない。空洞の“まなざし”は共有できないよ。
 先程、“謎”のシーンと書きましたが、『ツリー・オブ・ライフ』という映画の中には、『2001年宇宙の旅』級にブッ飛んだ映像というか、“地球に生命が誕生した瞬間”という文字通り宇宙規模の映像や、“恐竜たちの弱肉強食”という驚天動地の映像が随所に盛り込まれていました。はっきり言って難解ですわ。しかし、観始めた時には「わからん!」と匙を投げそうになった物語が、やがて“父と子の物語”に収斂してゆく様が、実に感動的だったのです。それに比べると、『トゥ・ザ・ワンダー』は全然普通というか、プロット自体は結構通俗的なメロドラマだし、一応リアリズムの枠内にある映画だから、すごくわかりやすいはずなのに。観始めた時に「おっ、これはわかるかも!」と思った物語が、一向に頭に入って来ないことへの当惑感。わからないものが思わずわかってしまって、わかるはずのものがサッパリわからない。そんな経験ありませんか? いやー、映画って実に不思議なものですね。こうして私は“TO THE WONDER”――自らの“ワンダー”に辿り着いたという次第。多分それは正解じゃない。
先程、“謎”のシーンと書きましたが、『ツリー・オブ・ライフ』という映画の中には、『2001年宇宙の旅』級にブッ飛んだ映像というか、“地球に生命が誕生した瞬間”という文字通り宇宙規模の映像や、“恐竜たちの弱肉強食”という驚天動地の映像が随所に盛り込まれていました。はっきり言って難解ですわ。しかし、観始めた時には「わからん!」と匙を投げそうになった物語が、やがて“父と子の物語”に収斂してゆく様が、実に感動的だったのです。それに比べると、『トゥ・ザ・ワンダー』は全然普通というか、プロット自体は結構通俗的なメロドラマだし、一応リアリズムの枠内にある映画だから、すごくわかりやすいはずなのに。観始めた時に「おっ、これはわかるかも!」と思った物語が、一向に頭に入って来ないことへの当惑感。わからないものが思わずわかってしまって、わかるはずのものがサッパリわからない。そんな経験ありませんか? いやー、映画って実に不思議なものですね。こうして私は“TO THE WONDER”――自らの“ワンダー”に辿り着いたという次第。多分それは正解じゃない。
むぎくら・まさき●LIGHTER/WRITER インタビューとかする人。音楽、映画、文学、その他。基本フットボールの奴隷。