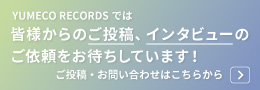前回、「別れ」について書いて生徒たちを送り出した気でいたら、今度は転勤でこちらが送り出される側になったでゴザル。いやあ、まったく予想していなかったので驚いた。
今年は桜が咲くのが早く、東京は3月中旬には開花宣言がされたと記憶しているが、米子の市街地でもそれに遅れること数日で咲き始め、3月末には満開だった。送別会からの帰り道に、そんな満開の桜を見ながら歩くのはなかなか良い気分だった。
そんなわけで、今回は「桜」について少々書いてみたい。
まず桜と言われて思い出すのが、「桜の樹の下には屍体が埋まっている!」という一文から始まる梶井基次郎の掌篇「桜の樹の下には 」だ。実は小さな頃にこれと同じようなことを親しい大人に言われたことがある。とても衝撃的だった。家の近くに桜がたくさん植わった公園があったので、ふとしたことで思い出すととても恐ろしかった。なぜその人はそんなことを幼い子供に言ったのか。ちょっとした悪戯心からだったのか。それとも、梶井基次郎の文章の持つ凄まじい影響力からつい口にしてしまったのか。今となってはもうわからない。代表作の「檸檬」もそうだが、なんだか彼の文章からは狂気を感じてしまう。あと、狂気と桜といえば、坂口安吾の『桜の森の満開の下 』も思い出される。桜の散り際を人の死に重ねることもあるので、桜と死は相性が良いのだろうか。
いや、そうとも言えまい。桜は華やかなものでもあるはずだ。例えば、谷崎潤一郎の『細雪 』に出てくる花見行楽の場面は、王朝文化が蘇ったかのような絢爛豪華な世界へと連れて行ってくれる。まさに夢のような世界だ。
そうそう、王朝文化と桜といえば、谷崎潤一郎が好きだった「新古今和歌集 」を代表する歌人であり、「ねかはくは 花のしたにて 春しなん そのきさらきの もちつきのころ」と詠んだ西行のことも忘れてはならないだろう。「西行桜」という能の演目で西行は桜の精に諭されたりしているし、桜に関する歌も多く、桜とセットにして語られることの多い人だ。個人的にも桜と言って思い出す人物のトップだろう。そんな西行には、彼の伝承を集めた『西行物語 』もあるし、瀬戸内寂聴の『白道』や白洲正子の『西行 』もあるけれど、西行を扱ったもので私が一番好きなのは辻邦生の『西行花伝』だ。辻邦生の透明感あふれる文章は日々の生活でささくれだった心を鎮めてくれる。700ページを超える分厚い本だが、彼の文章に浸っているとついつい時が経つのを忘れてしまう。
あと、桜を扱った小説といえば、宇野千代の『薄墨の桜』も印象深い。岐阜に実在する薄墨桜をめぐる人間模様を描いた短篇だ。実在の人物も出てきたりするので、現実と虚構が入り交じってなかなかインパクトのある作品に仕上がっている。文体のせいもあり、文章を読んでいると言うよりは話を聞いている感じがする。
その他には、水上勉の『櫻守 』もお薦めしたい。『小林秀雄講演 第3巻』にも出てくる「桜博士」として有名な笹部新太郎が、この小説では竹部庸太郎として出てくる。桜を扱った小説といえばまずこれを上げる人も多いのではないだろうか。関西弁が効果的に使われていて、登場人物たちの心情が読み手の心の奥深くに染みこんでくるような気がする。桜を守るために精も根も尽くす主人公・弥吉の姿には、滅びゆくものに対する著者の哀惜の念が込められているのではないだろうか。
今回、桜といって思いつくものを思いに任せて書いてみたけれど、さらに踏み込んでみたい方には山田孝雄の『桜史 』や小川和佑の『桜の文学史』をお薦めしたい。前者は昭和16年刊ということもあって文語文で読みにくいかもしれないがそんな欠点を補って余りある情報量だし、後者は古代から渡辺淳一までがコンパクトにまとめられている。きっと両方とも桜に関する良いブック・ガイドになってくれるでしょう。散った桜をしのんで、どれか1冊いかがですか。
のま・つとむ●東京生まれ。米子在住。学校図書館に勤務。引き継ぎやらなにやらでドタバタしてて読めず聴けずの今日このごろです。峠の桜はまだ満開で、それを見るのが通勤時の楽しみ。あと、桜も良いですが香りのある梅も負けず劣らず好きです。